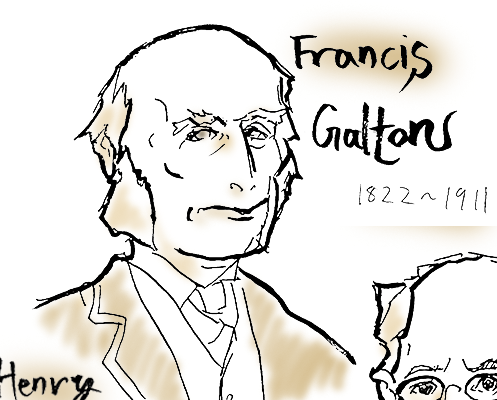シャーロック・ホームズ・シリーズが精力的に書かれていた1890年代の前半のイギリスでは、まだ事件の捜査のうえでの証拠として指紋をほとんど用いていませんでした。※2
1840年に、バートランド・ラッセルの曾祖父にあたるウィリアム・ラッセルが睡眠中に殺害されたときに、地方医師のロバート・ブレイク・オーバーがスコットランド・ヤードに手紙を書き、指紋を確認するように提案しているようですが、この頃はまだ指紋の有効性が確認できておらず捜査には取り入れていなかったようです。※1
その後、1892年に指紋分析を使用して解決した最初の既知の殺人事件あり、インド警視総監で後にスコットランドヤード警視総監に栄転するエドワード・リチャード・ヘンリー卿が実用的な指紋検索法を実施し、そのヘンリー卿にちなんだ指紋局が1897年設立されて捜査に使われるようです。
しかし、その少し前1880年にネイチャー誌でハーシェルという人の記事が載り、人体の統計について研究していたゴールトンは統計的に指紋の有用性を見出し、また1892年にアメリカからイギリスに渡ってきた南方熊楠がネイチャー誌において指紋は東洋で古くから使われていたという『拇印考(The Antiquity of the “Finger-Print”Method)』という論を寄稿しています。
■①心理学者とゴールトン■
フランシス・ゴールトン(Francis Galton、1822-1911)は、現在では統計学の分野では回帰分析や相関を作った人として名前が残され(相関係数rはゴールトンの命名に因む)、特に親と子供の身長をデータ化して「背の高い親から背の高い子供が生まれるのではなく、平凡に近づいていく」という「平凡への回帰」という考えたことが有名です。
この「平凡への回帰」1884年に、国際健康博覧会(The International Health Exhibition)がロンドンで開催される際、この近くに人体測定研究所を設立して多くの人体のデータを集めました。
国際健康博覧会は、衛生と公衆衛生におけるビクトリア朝の発展を強調することに重点を置き、当時の他の国と比較して、国の先進的な公衆衛生の取り組みを展示することができたようです。日本も出展していて豆腐製品を出しているようです。
この機会を利用して、ゴールトンは人体測定実験室(Anthropometric Laboratory)を設立しました。この実験室の目的は「人間の主な身体的特徴を測定し、記録すための器具と方法の単純さを一般の人々に示すこと」にあると述べ、利用者は入場料を支払った後、機能的な流れ作業の中で身長、体重、視力など身体的特徴が測定されたようです。個人と家族の情報をフォームに記入し、髪や目の色を記録したり、肌の鋭さ、色覚、奥行きの知覚、視力、聴覚の鋭敏さや最高可聴音を調べ、触覚、呼吸能力やパンチ力や両手で引っ張る力握る力なども調べ、最後に座高と身長を調べたようです。
この実験室は、革新的な測定技術を採用してなかったようですが、限られたスペースを活用してスムーズにさらに多岐に渡って測定できたというところが特徴だったようです。ゴールトンにとっては人体測定のデータ収集が目的でしたが、利用者にとっては身体的特徴を測定することは、より家庭的なレベルで、子供たちが適切に発展していることを確認するのに役に立つとゴールトンは述べているようです(このような部分から親子の利用者が多かったのではないでしょうか)。
そして、おそらくこの時のデータを使って親子の身長データから「平凡への回帰」を見出しています。1885年9月の英国科学振興協会(British Association for the Advanvement of Science)の会議で、セクションH:人類学の会長を務めていたため代表演説で「平凡への回帰」を述べているようです。また1886のJornal of the Anthropological Institute Vol.15において親子の測定データをまとめたグラフと楕円を描き入れたグラフを形成していたりします。
また1888年にもサウスケンジントン博物館のサイエンスギャラリーに研究所を設立して、参加者は少額の料金を払い測定により自分の長所と短所に関する知識を得ることができるシステムを取って、データ収集を継続していたようです。※4
近代心理学は、今までカタチの無かった心の作用を、実験や測定によりデータ化してそれを統計的に分析することで成り立ちましたが、ゴールトンのこの仕事もそれに近いように感じます。
おそらくそのようで、1879年ライプツィヒ大学で初の実験心理学の研究所を設立する事で近代心理学のはじまりとされるヴントのもとで、1883年頃からアシスタントとして働いていたジェームズ・マックイーン・キャッテル(James Mckeen Cattell 1860-1944)がゴールトンの研究所に働くことを望み、測定などからの研究に参加したというのがそうだと思います。※5
■②指紋学とゴールトン■
1880年にイギリスの『ネイチャア』誌(11月25日号)に、インドベンガル地方の行政官だったハーシェルのノートが掲載されたようです。
彼は20年間にわたり、現地雇用者の給料の二重取りを防ぐために指紋押捺制度を導入して成功していたようです。これは、イギリス人からみてベンガル人の顔が見分けにくいことと、署名できない事への対策であるとしたようです。※3
一方で、この論文の1か月前にも、ヘンリー・フォールズ博士によって法医学での使用の可能性の提案の論文がネイチャー誌に掲載されたようです。
ヘンリー・フォールズは医療宣教師で、1874年(岩倉遣欧使節団が返ってきた頃)に来日し日本で最初の英語を話す伝導所を設立し、病院と日本人の医学生のための教育施設を設置した人です。ジョセフ・リスターの消毒法を日本の外科医に紹介するのを手伝ったりしたようです。
大森貝塚を発見するエドワード・モース(1877年来日)が友人で、共に考古学的発掘にでかけているときフォールズは古代の粘土片に残った職人の指紋などから、自分の指先や友人の指先など隆起のパターンは人それぞれであることに気付いたようです。
そしておそらく1880年に『ネイチャー』誌(10月28日号)にこのアイディアを投稿したのだと思います。
またチャールズ・ダーウィンもフォールズの友人であったようで、ダーウィンに指紋識別のアイディアを深めようと相談しました。そして、ダーウィンはこのアイディアに取り組むことを断ったが、従兄弟であるゴールトンがおそらく身体測定の研究所などを発足して研究していたのを聞いたからか、ゴールトンにその指紋識別の可能性を伝え、ゴールトンはロンドン人類学協会に転送しているようです(これにより指紋識別のアイディアはフォールズなのかゴールトンなどがもめごともあったようです)。
その後、フォールズは1886年に英国に戻り、スコットランドヤードに指紋識別の概念を提案したようですが、却下されています。※6
一方、ゴールトンはフォールズの報告と、ハーシェルが蓄積していた20年分の資料を手掛かりにして、指紋が個人によって異なりまた不変であることを確認したようです。※3
ゴールトンは1888年の王立研究所の論文と、三冊の本(1892『指紋』、1893『Decipherment of Blurred Finger Prints』、1895『Fingerprint Directories』)において、2人の人物がお暗示ア指紋を持つ確率を推定してようです。また指紋の遺伝率と人種差も研究したようです。更に、指紋の共通パターンを特定し今日まで生き残っている8カテゴリーの分類システムを採用したようです。※4
他にも、指紋はそれぞれの個人に特有のものであり、また一生を通じて不変であるという観察・実験の結果も述べているようです。※2
■③南方熊楠と『拇印考』■

一方、1886年にアメリカに行き、ゴールトンが指紋について発表しはじめた1888年頃からイギリスへ行く可能性も考え『ネイチャー』誌を購読し始めていた南方熊楠も、1892年にイギリスに渡り『ネイチャー』誌への投稿を続ける中、指紋に関する記事を投稿することを考え始めます。
『ネイチャー』誌において、まずフォールズが1888年10月28日号で個人識別のための指紋の研究の着想を報告したため、以前から研究し植民地執政官としてインドで実践していたウィリアム・ハーシェルが1888年11月25日号で実践例の報告を投稿しました。
そして1892年のゴールトンの『指紋』によって指紋法が世に広く知らしめることになったようです。
しかし一方では、この方法は東洋で普通に用いられてきた、とする意見が出はじめていたようです。1894年9月には『19世紀』誌においてスピアマンが「指紋法は中国人が発明したもの」という説を掲げ、1894年11月の『ネイチャー』誌においてハーシェルはそれを否定したりしていました。
そこで1年前に「東洋の星座」という記事を『ネイチャー』誌に寄稿していた南方熊楠が、1894年12月27日号の『ネイチャー』誌に「「指紋」法の古さについて(The Antiguity of the “Finger-Print” Method)」という記事を寄稿し、「私はいくつかの史料から、中国人発明説を裏付けると思われる事実を収集している」と述べ、『大宝律令』とそのベーストなった中国の『永徽律令』を挙げ、さらに『水滸伝』を用い論証しています。※2
このように、当時のイギリス人にとっては拇印による身分証明という方法は今までにない新しいものであったようです。※7
■④南方熊楠と人類学とネイチャー■
『ネイチャー』誌は1869年にイギリスの天文学者ノーマン・ロッキャーによって創刊されたようです。ただ、当時はもう科学専門誌は存在していて、『ネイチャー』誌はそれほど新しい発想のものではなかったようですが、読者の投稿を取り入れたりするなどの工夫が長く続くものとなり、現在では有名な科学専門誌となっているようです。
初期の『ネイチャー』誌は、「Xクラブ」というダーウィンの進化論や共通祖先の存在を強く支持するメンバーによって書かれた記事によって構成されていたと言われています。Xクラブは1864~1893年くらいまで活動していたようなので、おそらく熊楠が寄稿し始めた1893年には執筆陣が変わりつつあったようですが、恐らくその気風は残っていたと思います。
「Xクラブ」は「ダーウィンのブルドック」とも言われた強いダーウィンの擁護者トマス・ヘンリー・ハスクリーが主催し、ダーウィンと最も親しい植物学者ジョセフ・ダルトン・フッカーや、進化論を社会学に適応したハーバート・スペンサーなどがいます。※8
南方熊楠も渡英する際にはハーバート・スペンサーの文明論を述べていて、アメリカにおいてはダーウィンの多くの著書と、ダーウィンと同じタイミングで進化論を着想したウォレスの著作を読んでいます。
そして南方熊楠が渡英した1893年には英国人類学の誕生によって湧き上がっていたようです。英国人類学は、1859年『種の起源』の生物学の方法にヒントをえて、社会のかたちや神についてのさまざまな考えなどを、ひとつのスペシーズ(種)のようにたかいに比較し、おたがいのあいだに進化の順序づけをおこなうという合理主義的方法がバックボーンに合ったようです。
つまり、『種の起源』とその方法と結びついた博物論が英国で流行っていて、その流れが『ネイチャー』誌にも表れていて、さらに同じようにダーウィンやスペンサーに触れあっていた熊楠はその英国人類学に興味を持ち、東洋の博物的知識をもとに英国人類学の見識を修正しようと考えたのだと思い、その流れとして『ネイチャー』誌に寄稿していたとも考えられると思います。
英国人類学の誕生は、19世紀の大英帝国が人類学的知識のトプランナーにおどりでていたのが大きな要因のようです。この時代の英国は、驚くような勢いで、地球上のあらゆる方角の「前産業革命」的世界にむかって、植民地主義的な拡張をこころみていたようです。
そのため、いままでじゅうぶんに調査されたことのない地域もふくめて、じつにおびただしい量の民俗学的情報が、集められていたようです。
そして、それがこの時代になるとしだいに、「フォークロア学」へと成長をとげてきたようです。
この新しいフォークロア学派は、農民や漁師や猟師の伝承の中に、未開社会の思考法とも共通するものが、たくさんあることを、みいだしていたようです。自分たちの文明の基礎には、未開社会と共通の「プリミティブ・マインド」の古層があり、それはキリスト教によっても破壊しつくされることはなく、農民たちばかりでなく、シェークスピアの中にも、また多くの詩人たちの中にも、それは生きつづけていたということを、フォークロア学者は発見しつつあったようです。
1871年にシュリーマンがトロイ遺跡を発掘され、ギリシア古典学の方法論は、根底からゆらいだ。英国の、とくにケンブリッジの研究者たちは、古典研究の新しい方法論を模索出していた。そして、同じ1871年タイラーが『未開文化(原始文化)』が出版され、若い古典学者フレーザーがケンブリッジに入学した1873年頃は、共通な未開心性というものの側から、古典を読み解いていくという方法が、可能ではないかという傾向がしだいに明確になりだしていたようです。
そしてフレーザーが1890年に『金枝篇』を出版し、新しい人類学時代をひらく本として、おおいに注目を集めていたようです。
そういう動きから英国人類学は、かたちづくられてきたようです。
そして、その新しいタイプの学問として、生まれたばかりの英国人類学に南方熊楠は1893年に渡英した時にジャストタイムで遭遇し、すっかり魅了されたようです。※7
そのような流れが、南方熊楠とネイチャーを結びつけたのだと思います。
そして、フランシス・ゴールトンも1885年5月10日ロンドン人類学会会合で、フレイザーが「魂に関する未開理念を例証する埋葬習慣について」を発表する際、その会合で司会をしている所からみると、ゴールトンの人体測定による統計的アプローチも人類学の違う方向のアプローチだったのかもしれません。
そしてその会合には、「Xクラブ」のハーバート・スペンサーと『未開文化』を書いたタイラーも出席しています。※10
※余談ですが、熊楠もロンドン抜書においてゴールトンの『指紋』を抜き書きしています。
【参考文献】
※1…英語版ウィキペディア「Finger print」
※2…『南方熊楠英文論考[ネイチャー]誌篇』南方熊楠が書いたのを飯倉照平が監修2005.12.20集英社
※3…『知の統計学2』福井幸男1997.6.30共立出版
※4…英語版ウィキペディア「Frances Galton」
※5…英語版ウィキペディア「James Mckeen Cattell」
※6…英語版ウィキペディア「Henry Faulds」
※7…『南方熊楠を知る事典』松居竜五ら1993.4.20講談社
※8…英語版ウィキペディア「Nature(journal)」
※9…『南方民俗学-南方熊楠コレクション第二巻』中沢新一(編)1991.7.25河出書房
※10…navymule9.sakura.ne.jp