イギリスの国会議事堂(ウェストミンスター宮殿)の有名な時計塔「ビッグ・ベン」。
この「ビッグ・ベン」のデザインを担当したのが、オーガスタス・ピュージンで、彼は大英帝国のゴシック建築の復興(ゴシック・リバイバル)の建築家でした。
当時、イギリス建築界では、ギリシャやロマネスクなどルネサンスが理想とした建築を目指す新古典派と、中世の建築を理想とするゴシック派が争っていました。
現にこの国会議事堂も、1834年に大火事が起ったことを端として作られ、デザインは新古典派にするか、ゴシック派にするか大きな論争となりました。論争の結果、ゴシック建築にすべきというような方向になったにも関わらず、設計に選ばれたのは新古典派のチャールズ・バリーと「ビッグ・ベン」を設計したゴシック派のピュージンの2人が選ばれるという混迷ぶりでした。
【1.建築のデザイン】
結果、できた国会議事堂の建物を見てみると、基本的な構成は左右対称や長方形のファサードを持った新古典派的なデザインがベースとなっています。ピュージン自身も、できた建物は基本的にギリシア様式で、細かいところでチューダー様式(中世とルネサンスの間に登場した建築様式で、ゴシック建築を新古典派的要素によって構成する様式)をほどこした、と言ったほどで、ゴシック・リバイバルの世界遺産とされていますが、一筋縄ではいかなかった当時の様子を建築が表しているようです。
しかし、この国会議事堂の右側にある大きな時計塔「ビッグ・ベン」(エリザベス・タワー)は、ピュージンが作った作品となっています。尖った形の垂直に伸びた塔と壁のデザインなどまさしくゴシック建築なのですが、当時の建築家は家具のデザインなども行っていて、時計塔の文字盤などもピュージンがデザインしています。
因みに左側にある大きな塔「ヴィクトリア・タワー」はゴシック様式で作られていますが、チャールズ・バリーが基本的にデザインして、ピュージンはディティールをデザインした程度のようです(国会議事堂の真ん中の大きな建物のもチャールズ・バリーがデザインし、内装などをピュージンが担当。但し、建築自体は新古典派的)。この時代、特に公的な建物ほど新古典派とゴシック派の折衷のような役割分担になることも多かったようです。
【2.ピュージンについて】
さて、そのピュージンなのですが、1812年生まれと大体チャールズ・ダーウィン(1809生まれ)世代です。父がフランス革命によってフランスからイギリスに移住してきたようで、父もゴシック建築に関する著作を書いていました。ピュージン自身も父の事務所で働くのですが、独立後教会のゴシック建築を多く作っていくことになります。
そして1829年には法律が改訂され、英国国教会でなくてもキャリアとして成功できる道が開かれました(逆に以前はカトリックなどでは制限があった)。そのため、ピュージンも1834年にカトリックに改宗し、カトリック教会関係の仕事が多く依頼されるようになり、有名になっていきます(ゴシック・リバイバルが起こった経緯としてこのようなカトリックと国教会の宗教関係の争いが発端の一つと成っています)。そしてゴシック建築に関する著作や、本格的な教会建築を作っていきます。
これによって、ゴシック派として名声が上がり、国会議事堂の設計の選考に選ばれることになるのです。
ただし、国会議事堂の建設中にゴシック建築に関してセンセーションを起こした評論を書いたラスキンは、1851年に出版した『ヴェニスの石・1巻』の付録で、ピュージンがゴシック建築家としてかなり低いという評価をつけた関係もあり、その翌年ピュージンが亡くなった後には世間から忘れされていったようです。
ただ、『ヴェニスの石・2巻』に収録されている『ゴシックの本質』という文章の中で述べているゴシック理想とピュージンのゴシック建築はかなり類似しているように感じ(St Chad’s Cathedral, Birminghamとかは特に感じる)、実際ピュージンを擁護する人からはラスキンに、ラスキンの理想と近いものがあるではないかと批判し返されているようです。
また、建築家にもピュージンの意志を継いだものもいて、その一人にウィリアム・モリスが1857年に働くことになるG.E.ストリートもその一人です。ストリートは後にヴィクトリア朝のゴシック復興の第一人者とも言われ、ピュージンの著作を念入りに研究していて(ただストリートはカトリックでなく英国国教会のようです)、有名なロンドンの王立裁判所などの建築にもピュージンの影響が現れているようにおもわれます(奇しくも王立裁判所の設計者選考でも、国会議事堂のデザイナーの一人チャールズ・バリーと争っていて、結果ストリートが一人でデザインすることになっています)。
現在、「ビッグ・ベン」は改修工事中で、2021年に完了予定ですが、また姿を見れるのが楽しみですね。
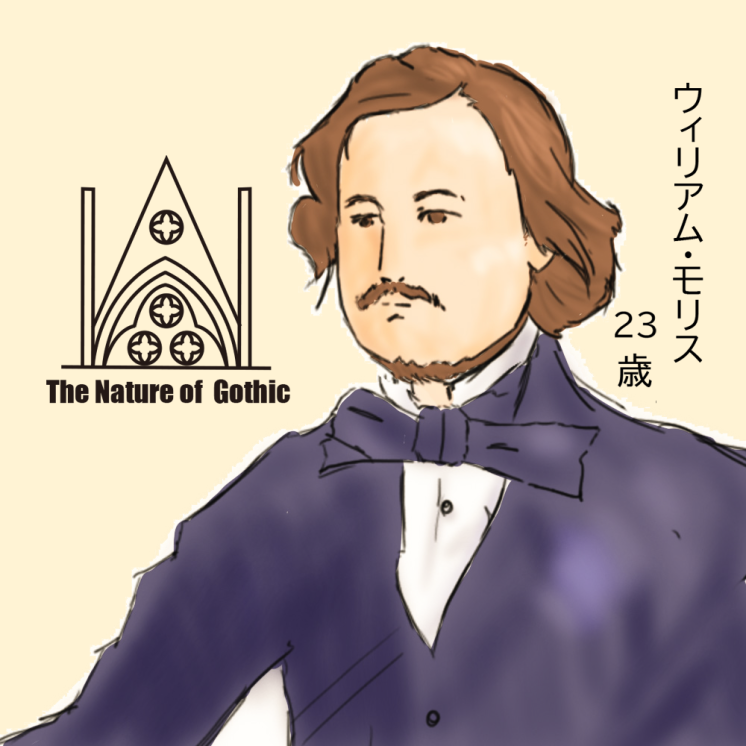
人類は自分がなぜこの世に存在しているのか、という問いを解こうとする努力をけっしてやめることはないだろう。
だがそれも「なぜわれわれはかくも悲惨な境遇に生まれたのか」と問うのではなく、むしろ「なぜわれわれはかくも幸福な身に生まれたのか」と問えるようになったときに、もっと穏やかで満ち足りた気分でその問題にむかえるようになると私には思える。
、、、とウィリアム・モリスは、ジョン・ラスキンの『ゴシックの本質(The Nature of Gothic)』の著作の序文で解説しています。
『ゴシックの本質』はウィリアム・モリスがオックスフォード大学に在学中に読んで衝撃を受けた本でした。
モリスが大学生だった時、イギリスでは「ゴシック・リバイバル」と言い中世のゴシック建築が改めて再評価されるブームが起こっていました。
元々は、イギリス内でのアイディンティティの確立のためや、国内の宗教の改革の関係によってなされた動きから始まったブームでした。そのため、イギリスにおいてはゴシック建築家が新機軸として注目されていました。
その中で、ジョン・ラスキンという評論家が、ヴェネツィアの北方ゴシック建築の受容という観念から改めてゴシックを哲学的に考えようとしたのが『ゴシックの本質』です。
勿論、ゴシック建築を扱った著作なのでゴシック建築の普遍的な形態なども明確に分析されていますが、その本を読んで衝撃を受けたウィリアム・モリスは、ラスキンの「倫理的・政治的側面を注目してほしい」と解説しています。
というのは、冒頭で述べたようにラスキンの『ゴシックの本質』は、自分自身の存在理由を仕事での満足度によってポジティブに考えられる糸口を述べてもいるからです。
ラスキンは『ゴシックの本質』で、現在の大英帝国は「世界の工場」と言われる程産業革命が行われてきているが、労働者の精神状態はかつての奴隷貿易の奴隷以上にツライものになっていると述べています。奴隷は主人の命令を聞かなくては行けなくてはならないが、仕事のやり方に創意工夫をする自由が多少はあった。しかし、今はベルトコンベアの部品の一部のように何の創意工夫を凝らす自由さえ奪われている、というような事を述べています。同様に封建主義の農夫よりも現在の労働者は酷い状況にいると述べています。
なぜそんなことが起こってしまったのかと言うと、完璧な商品こそが価値があるという考え方が工場化が進むと徹底されてしまい、アイディアを出す人とそれをマニュアル通りにこなす人に分かれてしまったためというような事を述べています。
それは、芸術(絵画)の分野で言うと「ルネサンス」がそれにあたります。「ルネサンス」は人間の精神を解放する(価値のあるものだとする)流れを作りましたが、一方で遠近法や美術解剖など絵画の良さを決める統一した基準が登場し、ダ・ヴィンチやミケランジェロ、ラファエロなどが作り出したような至上な芸術を模範とすべしというような風潮を作ってしまった面もありました。
そのため「ルネサンス」以後、絵画においてはダ・ヴィンチやミケランジェロ、ラファエロを基準として絵画の価値を決めるようになってしまったのです。つまり、その基準に到達しない絵画は価値のないものだと思われるようにもなってしまったのです。
そのような傾向が、建築にもルネサンス付近に起こっているため、中世のゴシック建築の時代にまで遡って、労働者(職人)の仕事のやりがいを問い直さなければならないとしているのがラスキンなのです。
今は一流の人のアイディアを工場で忠実に生産されるため、消費者は完璧なものを手に入れるようになりました(現に当時のイギリスでは完璧な規格の商品が手に入る事が他国に対しての一つの優越感でもありました)。しかし、果たして工場で働く労働者は楽しく仕事ができていたのであろうか?
中世のヴェネチアのガラス細工は、手造りであったため確かにガラスの食器などは形がいびつでした。しかし、いびつだから言って価値のないものではなく、職人が創意工夫を凝らしながら生み出せる産物であり、生産した職人には誇りですらありました。そして、その頃は消費者もその職人の創意工夫を喜んでいさえいました。
しかし、今はいびつであることで商品価値がないと思うなんて、少し歪んでいませんか?、、、ということをラスキンは「ゴシック建築」を通して問いています。
確かに、後に手作りの商品のすばらしさを広めることになるウィリアム・モリスが「倫理的政治的側面を注目するように」と言っていたのもなんだか、納得します。
勿論、ゴシック建築の外観の分析も非常に読み応えのあるものです。自然に対する愛が建築に反映され、意匠に活かされているなどは、ゴシック建築から影響を受けたウィリアム・モリスが「アール・ヌーヴォー」という有機的な曲線を生かしたデザインブームに寄与している理解に繋がるところなどがあります。
そして、ウィリアム・モリス自身もこのラスキンの『ゴシックの本質』の影響から、大学を卒業した23歳(1957年)、「ゴシック・リバイバル」の流れでゴシック建築を最も勢いよく作っているオックスフォードのG.E.ストリートのもとに働きに行くほど心を揺さぶらて行くのです。




