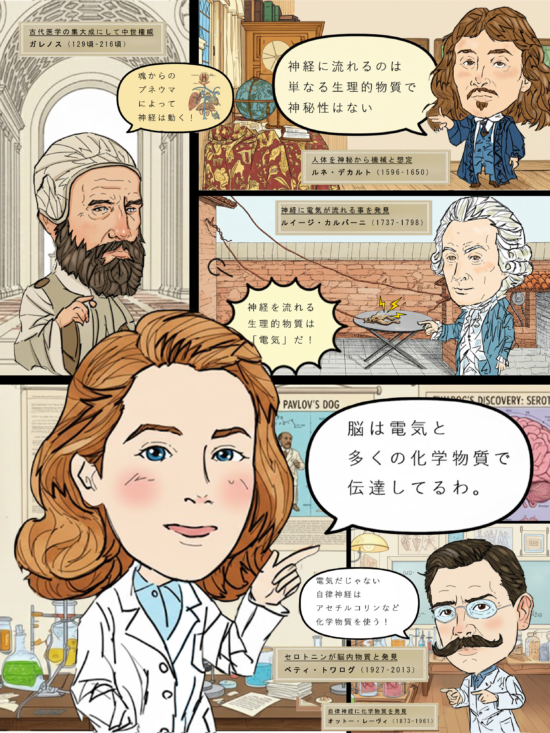ダーウィンが進化論を考える際、地球の年齢が重要な要素であった。宗教革命以降聖書から算出した紀元前4000年というのが地球の始まりの定説であったが、それよりもはるかに長い期間を想定する事によって生物の進化が科学的なものとして考えられると思ったからだ。
ダーウィンがビーグル号の航海に出るころには、地質学の発展が進み、地球の昔の時代区分を想定する科学的な方法が確立し始めていた。ダーウィン自身も地層を観察することでこの流れを体感した。
ダーウィンがビーグル号の航海を決意したのはフンボルトの著作によるとされている。フンボルトは地質学の研究と共に地理的影響がどのように生物の分布に影響を与えるか研究した人でもあった。
| 目次 |
| ①ビーグル号の航海に向けてのダーウィンの関心 ②ビーグル号の航海での体験 ③ダーウィンの地球の年齢の推定 |
■①ビーグル号の航海に向けてのダーウィンの関心■
ダーウィンがケンブリッジ大学トリニティ・カレッジに通っていた頃、1831年8月アダム・セジウィックの指導のもと、ウェールズ北部で地質調査を行った。アダム・セジウィックはその後、ウェールズ地方が古代ローマ時代に「カンブリア」と呼ばれていた事から、1835年頃に「カンブリア紀」を提唱している。「カンブリア紀」とは古生代の最初の紀で、約5億4200万年前から約4億8830万年前までの期間を指し、動物が爆発的に進化した時代として知られ、特に初期には「カンブリア紀の大爆発」と呼ばれる生物多様性の急速な増加が見られた。この時代には、外骨格を持つ無脊椎動物が多様化し、三葉虫類が栄えた。
そしてこの地質調査は、ダーウィンにとって、地質学の基礎を教えられ、地層の観察方法が身につくこととなった。
地質調査の同年1831年にケンブリッジ大学を卒業し、12月にビーグル号の航海に参加する際、ダーウィンは『地質学原理』1巻をイギリスを発つ前に船長フィッツロイから贈られている。ロバート・フィッツロイは、ビーグル号の艦長として、当時のイギリス海軍の規則に従い、乗組員と個人的な接触を避けることが求められていた。しかし、精神的な孤独を避けるために、フィッツロイは話し相手として博物学者を同行させることを望み、ダーウィンが選ばれたのだ。フィッツロイはダーウィンにライエルの『地質学原理』を紹介し、地質学的な観察を促すなど、ダーウィンの学問的成長にも影響を与えた。
ライエルは後の1839年に「更新統」という地層を命名している。これは軟体動物化石群に現生種が90%以上含まれる地層のことで、新生代第四紀の更新世の概念に結びつくことになる。これは1839年頃には、地質学者や科学者が氷河時代(1837年スイスの地質学者ルイ・アガシーがジュラ山脈の調査から提唱)の存在を認識し始め、関連する研究が進展していた事と関係していると思われる。
このように地球の昔の時代区分の命名がすすむ時代にダーウィンは位置し、その流れをダーウィン自身もビーグル号の航海で地質学的な観察を通して体験する事となる。
そして、チャールズ・ライエルの著作『地質学原理』は、地球の地形が長い時間をかけた斬新的な変化によって形成されるという「斉一説」を提唱している。ライエルの主張する「地球は長い時間をかけて変化してきた(地質学的変化には膨大な時間が必要)」という考えは、ダーウィンが生物進化に必要な膨大な時間の存在を理解する助けとなった。
また、ダーウィン自身によるとフンボルトの著作が彼の探求心を刺激したと述べており、フンボルトの影響を受けてビーグル号に乗船する決意をしたとされている。ダーウィンはフンボルトの著作を読み、南アメリカの自然や地理についての情熱を抱くようになった。ダーウィンは『新大陸赤道地方紀行』(『南アメリカ旅行記』)を手がかりに、ビーグル号の航海で観察や調査を行ったとも言われる。
フンボルトの『南アメリカ旅行記』は、彼の生物地理学の体系化に大きな役割を果たした。フンボルトは1799年から1804年にかけて南アメリカを探検し、その際に多くの植物や動物を発見し、気候や地理が生物の分布に与える影響を研究した。植物地理学や動物地理学の分野で、フンボルトは生物とその生息地の関係を明確にし、生物地理学の基礎を築いた。
このように、地質の研究と共に気候や地理が生物に与える影響を研究しようとしたのがビーグル号の航海にむけてのダーウィンの関心だった。
■②ビーグル号の航海での体験■
1832年9月から1833年8月にかけて、ダーウィンはパンパス地域を含む南米大陸を横断し、地質学的調査を行う。アルゼンチン(南米の南東側)に着く。スミロドン(最後のサーベルタイガー)、トクソドン(サイやカバに似た大型草食哺乳類)、メガテリウム(巨大なナマケモノの近縁種)など絶滅した生物の化石を発見。
パンパスは地質学的に比較的安定した地域であり、地殻変動が少ないため、地層が長い時間をかけて堆積された痕跡が残っていた。また海洋堆積の地層を観察し過去にこの地域が海底であったことを読み取り、地層が形成された後に隆起したこと観察する。更に地上に生息する動物と似た化石が地下に埋もれていることを発見した(海洋生物が陸生に進化したか、陸生生物が海洋に流されたか)。
1835年2月20日にチャールズ・ダーウィンはビーグル号に乗船しており、チリのバルディビアに近い場所にいた際、チリでコンセプシオン地震が発生。地震後に海底が隆起してイガイが浜に取り残されていたことを観察した。潮間帯に生息していたムラサキイガイ(Mytilus)の死殻が高潮線より3m高い位置に残留しているのを発見し、これを地殻変動の指標として用いた。フィッツロイとダーウィンは、島の南部で2.4m、中部で2.7m、北部で3mの隆起を計測した。フィッツロイとダーウィンの記録は、プレートテクトニクス理論が確立される以前に、地震と地殻変動の関係を具体的なデータで示した先駆的な業績として評価されている。
1835年3月南米西岸の国チリのアンデス山脈(南米大陸の西側に沿って南北7500kmにも及び世界最大の山脈)横断の旅を決行。アンデス山脈では、火山活動が活発で、火山岩や地震活動が地層の形成や変化に影響を与えていることを観察した。アンデス山脈は地殻変動が活発で、山脈の形成や変動が地質学的なプロセスによって長い時間をかけて進んだことを観察した。これにより、地殻の隆起や沈降が地層の形成に影響を与えることを理解した。
1835年9月15日から10月20日までガラパゴス諸島(ガラバゴ=リクガメのスペイン語でゾウガメたちの島々という意味)に滞在。南太平洋エクアドルの西約900kmの太平洋に浮かぶ大小の島々と岩礁からなる火山によって生じた群島。サン・クリストバル島、フロレアナ島、イサベラ島、サンティアゴ島の4つの島に上陸。ラパゴス諸島では、ゾウガメ、フィンチ、ウミイグアナなど、特異な生物を観察した。これらの生物は南米大陸の生物に類似している一方で、島ごとに異なる特徴を持っていた。ゾウガメは島ごとに甲羅の形が異なることに注目した。フィンチはクチバシの大きさや形状に顕著な違いがあり、これが後に「ダーウィンフィンチ」として知られるようになった。ウミイグアナは 世界で唯一の海生イグアナに遭遇した。ダーウィンは、これらの生物が南米大陸から渡ってきたものであり、島の環境に適応して変化したと考えた(そのため哺乳類がいない)。これが彼の進化論の基盤となった。
ガラパゴス諸島のどの動物たちも南米大陸でみた動物たちと類似しているが、はっきりとちがうガラパゴス固有の亜種であり、その種類だけでいえば数は少ない。そして不思議な事に野生の陸上哺乳類の種がいない。進化論で説明すると火山の噴火で生まれたガラパゴス諸島は最初は生物がいなく風や波に乗って植物の種が運ばれ植物が繁栄する。するとそれを餌にする鳥類と、流木などにしがみついて島に上陸したカメやイグアナなどの爬虫類が辿り着く。しかし、長期間食料がなくては生きられない哺乳類は漂着できなかった。そして島にたどりついた動物たちは大陸とは違う適応をとげた。
大地が斬新的に変化するように、生物もまた小さな変化が積み重なることで進化すると考えるようになる。この「漸進的進化」の考えは、後に彼の自然選択や『種の起源』の理論構築に繋がった。
■③ダーウィンの地球の年齢の推定■
1859年、ダーウィンは『種の起源』初版で、地球の年齢を少なくとも3億年以上と推定。彼の推定は、当時の一般的な地球の年齢の見解(数千年)とは大きく異なっていた。海岸や川岸の土砂の堆積速度から、地形が形成されるのに数億年かかることを推測した。これは、当時の地質学者が化石や岩石の年代を正確に測定する技術がなかったため、地形の変化速度を観察することで地球の年齢を推定する方法を取ったため。
具体的なデータ源は、イギリス南部のウィールド地方における地質学的観察による。彼はこの地域の広大な谷(森林地帯)が海の波による浸食で形成されたと仮定し、その浸食速度を基に必要な時間を計算した。
ケルヴィン卿が熱力学を用いて地球の年齢を2000万年から4億年(具体的には9800万年と示したが不確定要素を考慮すると)計算し、ダーウィンの推定は批判を受けた。これによりダーウィンが『種の起源』第3版以降でこの記述を削除している(但し、現在は約46億年とされているため事実はダーウィンの方が近かった)。ダーウィンの推定が批判される理由は、当時の物理学的根拠に基づくケルビンの推定と比較して、地質学的観察のみに頼ったものであったため。特に、ケルビン卿の計算は数学的に健全とされていたが、ダーウィンの推定はより主観的で、具体的な計算方法が不明確であったため、批判を受けた。
時を経て20世紀中頃の放射年代測定技術の発展により、隕石や月の岩石の放射性同位体を用いた年代測定が進み、「約46億年」という推定が確立している。
以下は詳細版
目次
①ダーウィンと地質学原理
②ビーグル号での軌跡
③地球の年齢
■①ダーウィンと地質学原理■
チャールズ・ライエルの著作『地質学原理』は、地球の地形が長い時間をかけた斬新的な変化によって形成されるという「斉一説」を提唱している。そしてこの考えはダーウィンがビーグル号航海のときから大きな影響を与えている。ビーグル号で航海した南米のパンパス(アルゼンチンやウルグアイに広がる肥沃で平坦な大草原)からアンデスまでの地質学についてはすべてがライエルに重なるとも言われる程。ダーウィンは『地質学原理』1巻をイギリスを発つ前に船長フィッツロイから贈られている(フィッツロイは博物学の話し相手が欲しくヘンズローを通してダーウィンを紹介してもらっている。フィッツロイも『地質学原理』を気に入っていた)。
もともとダーウィンは1831年にアダム・セジウィックの指導のもと、ウェールズ北部で地質調査を行う。アダム・セジウィックはダーウィンがケンブリッジ大学トリニティ・カレッジに通っていた頃の指導者であったが、地質年代の「デボン紀」の名称を提案し、ウェールズ北部の地層を調査して「カンブリア紀」を命名した人でもある。実際この1831年のウェールズの地質調査から、その後1833年から1835年頃にこの名称を正式に「カンブリア紀」を提唱している。この地質調査は、ダーウィンが地質学的な変化は徐々に起こるという考えを理解する助けとなった。更にダーウィンがビーグル号での航海に備えるための重要な経験でもあった。ダーウィンはビーグル号の航海中もセジウィックと文通を続け、友好的な関係を保った。
またライエルが1839年に「更新統」という地層を命名し(軟体動物化石群に現生種が90%以上含まれる地層を発見)、これが更新世の概念に結びつくことになる。これは1839年頃には、地質学者や科学者が氷河時代(1837年スイスの地質学者ルイ・アガシーがジュラ山脈の調査から提唱)の存在を認識し始め、関連する研究が進展していた事と関係していると思われる。このように時代区分の命名がすすむ時代でもあったようだ。
ライエルの主張する「地球は長い時間をかけて変化してきた(地質学的変化には膨大な時間が必要)」という考えは、ダーウィンが生物進化に必要な膨大な時間の存在を理解する助けとなった。ビーグル号航海のとき、アンデス山脈で海洋生物の化石を発見し、大地が隆起する過程を考察している。また特にイングランド南東部の地形の形成が非常に長い時間をかけて行われたことを認識もしている。
最初に訪れたパンパスは地質学的に比較的安定した地域であり、地殻変動が少ないため、地層が長い時間をかけて堆積された痕跡が残っていた。また海洋堆積の地層を観察し過去にこの地域が海底であったことを読み取り、地層が形成された後に隆起したこと観察する。更に地上に生息する動物と似た化石が地下に埋もれていることを発見した(海洋生物が陸生に進化したか、陸生生物が海洋に流されたか)。
その後、アンデス山脈では、火山活動が活発で、火山岩や地震活動が地層の形成や変化に影響を与えていることを観察した。アンデス山脈は地殻変動が活発で、山脈の形成や変動が地質学的なプロセスによって長い時間をかけて進んだことを観察した。これにより、地殻の隆起や沈降が地層の形成に影響を与えることを理解した。
大地が斬新的に変化するように、生物もまた小さな変化が積み重なることで進化すると考えるようになる。この「漸進的進化」の考えは、後に彼の自然選択や『種の起源』の理論構築に繋がった。
ライエルの影響により、ダーウィンは進化論を科学的に裏付けるための長期的視点と証拠収集の重要性を学んだ。ウィリアム・スミス(イギリス地層学の父)やバックランド(メガロサウルスの発見者・ロンドン地質学会会長)、セジック(ダーウィンのケンブリッジ大学の師でカンブリア紀を提唱)らは洪水説から脱せなかったが、ライエルによって斉一説により近代地質学の真の確立になり、ダーウィンが最も深く影響を受けた先輩の科学者となる。
1831年にイギリスのデヴォンポート港から出航。
1832年カーボヴェルデに1月16日から2月8日まで寄港。ダーウィンはここで火山を観察し、航海記録の執筆を始める。
1832年2月からブラジル(南米の東側)に到着(4月まで)。
2月28日にブラジルのバイアにつき、州都サルヴァドルに着く。
ダーウィンはこのバイアでヘンズローから渡された『新大陸赤道地方紀行』(『南アメリカ旅行記』)を読む。ダーウィン自身によるとフンボルトの著作が彼の探求心を刺激したと述べており、フンボルトの影響を受けてビーグル号に乗船する決意をしたとされている。ダーウィンはフンボルトの著作を読み、南アメリカの自然や地理についての情熱を抱くようになった。。ダーウィンは『南アメリカ旅行記』を手がかりに、各地で観察や調査を行ったとも。
フンボルトの『南アメリカ旅行記』は、彼の生物地理学の体系化に大きな役割を果たした。フンボルトは1799年から1804年にかけて南アメリカを探検し、その際に多くの植物や動物を発見し、気候や地理が生物の分布に与える影響を研究した。動植物の分布と地理的要因を関連づける考え自体(生物地理学)は、フンボルト以前から存在していたが、彼がこの分野を体系的に研究し、理論化したことは確か。彼の研究は、後の生物地理学者たちに大きな影響を与えた。
フンボルトの生物地理学の体系化は、特に彼が南アメリカでの観察を通じて得た知識に基づいている。彼は、気候や地理的な要因が生物の分布にどのように影響するかを明らかにし、これを定量的な方法で示した。この研究は、彼の著書『コスモス』でも取り上げられており、自然の統一理論としてまとめられている。
『南アメリカ旅行記』は、フンボルトが得た多くの科学的知識をまとめたものであり、彼の生物地理学の体系化に直接的な影響を与えています。特に、植物地理学や動物地理学の分野で、フンボルトは生物とその生息地の関係を明確にし、生物地理学の基礎を築いた。
アマゾン熱帯雨林は南米アマゾン川流域に広がる世界最大の熱帯雨林(ジャングル)。アマゾンは地球上でもっとも多種の生物が生息していてその数は数百万とも言われている。
1832年7月26日から8月5日までモンテビデオに滞在。『地質学原理』第二巻が届く。
1832年9月から1833年8月にかけて、ダーウィンはパンパス地域を含む南米大陸を横断し、地質学的調査を行う。アルゼンチン(南米の南東側)に着く。スミロドン(最後のサーベルタイガー)、トクソドン(サイやカバに似た大型草食哺乳類)、メガテリウム(巨大なナマケモノの近縁種)など絶滅した生物の化石を発見。
1832年12月1日から1833年1月26日までティエラ・デル・フエゴ島に滞在。
1834年3月にフォークランドに寄港。『地質学原理』第三巻届く。
1833年4月から6月にかけて、ダーウィンはパンパス地域での調査に重点を置く。
1834年6月から7月にバルパライソ(チリ)に寄港し、ダーウィンは病気で療養。
1835年2月20日にチャールズ・ダーウィンはビーグル号に乗船しており、チリのバルディビアに近い場所にいた際、チリでコンセプシオン地震が発生。地震後に海底が隆起してイガイが浜に取り残されていたことを観察した。潮間帯に生息していたムラサキイガイ(Mytilus)の死殻が高潮線より3m高い位置に残留しているのを発見し、これを地殻変動の指標として用いた。フィッツロイとダーウィンは、島の南部で2.4m、中部で2.7m、北部で3mの隆起を計測した。フィッツロイとダーウィンの記録は、プレートテクトニクス理論が確立される以前に、地震と地殻変動の関係を具体的なデータで示した先駆的な業績として評価されている。
1835年3月南米西岸の国チリのアンデス山脈(南米大陸の西側に沿って南北7500kmにも及び世界最大の山脈)横断の旅を決行。地層の中に会の化石を発見。
1835年9月15日から10月20日までガラパゴス諸島(ガラバゴ=リクガメのスペイン語でゾウガメたちの島々という意味)に滞在。南太平洋エクアドルの西約900kmの太平洋に浮かぶ大小の島々と岩礁からなる火山によって生じた群島。サン・クリストバル島、フロレアナ島、イサベラ島、サンティアゴ島の4つの島に上陸。ラパゴス諸島では、ゾウガメ、フィンチ、ウミイグアナなど、特異な生物を観察した。これらの生物は南米大陸の生物に類似している一方で、島ごとに異なる特徴を持っていた。ゾウガメは島ごとに甲羅の形が異なることに注目した。フィンチはクチバシの大きさや形状に顕著な違いがあり、これが後に「ダーウィンフィンチ」として知られるようになった。ウミイグアナは 世界で唯一の海生イグアナに遭遇した。ダーウィンは、これらの生物が南米大陸から渡ってきたものであり、島の環境に適応して変化したと考えた(そのため哺乳類がいない)。これが彼の進化論の基盤となった。
ガラパゴス諸島のどの動物たちも南米大陸でみた動物たちと類似しているが、はっきりとちがうガラパゴス固有の亜種であり、その種類だけでいえば数は少ない。そして不思議な事に野生の陸上哺乳類の種がいない。進化論で説明すると火山の噴火で生まれたガラパゴス諸島は最初は生物がいなく風や波に乗って植物の種が運ばれ植物が繁栄する。するとそれを餌にする鳥類と、流木などにしがみついて島に上陸したカメやイグアナなどの爬虫類が辿り着く。しかし、長期間食料がなくては生きられない哺乳類は漂着できなかった。そして島にたどりついた動物たちは大陸とは違う適応をとげた。
その後ニュージーランド、オーストラリア、モーリシャス島とケープタウン、セントヘレナ(ナポレオンの墓所を訪問)、バイーア(再訪)、カーボヴェルデ(再訪)、アゾレス諸島を経由してイギリスのファルマス港に帰着する。
※『まんがで読破 種の起源』2009.7.10バラエティ・アートワークス、イーストプレス 『ダーウィンが信じた道』エイドリアン・デズモンドら・(訳)矢野真千子ら2009.6.30NHK出版 参照
■③地球の年齢■
16世紀には宗教改革が起こり、旧来の教会に対する批判が高まった。そしてプロテスタントは教会批判のよりどころとすべく、聖書を注意深く読むようになり、批判を受けたカトリックも同様に聖書を読むようになった。
こうして人々の聖書や歴史への関心が高まった結果、聖書から地球の年齢を求める動きが再びさかんになった。マルティン・ルターは聖書を元に、天地創造の年を紀元前4000年とした。ジェームズ・アッシャーは年代紀を出版し、その中で天地創造の年を紀元前4004年10月23日前夜(土曜日)と記述した。この紀元前4004年という数字は欽定訳聖書にも注釈として書き加えられたため、英語圏の人々には広く知れわたるようになった。※1ニュートンものちに同様の解析(聖書の年代記を研究)をし、アッシャーの結果にお墨付きを与えている(紀元前約4000年前が天地創造の為計算すると約2000年現在から考えると6000年前が地球の歴史となる)。
一方で、地球の成り立ちについて聖書にとらわれない形で考察する動きもあらわれてきた。その嚆矢は1644年に出版されたルネ・デカルトの『哲学原理(英語版)』とされている。その後、ロバート・フックやゴットフリート・ライプニッツも化石の研究などから地球の形成を考えた。フックは顕微鏡を用いて化石と活木の構造を比較し、化石が生物起源であることを認識した。化石の研究を通じて、地質学的な観察を深め、地球の歴史を理解しようとした。
しかし地球の年齢について記したのはフランスの外交官ブノワ・ド・マイエだった。
ド・マイエは、自らの死後の1748年に匿名で出された書『テリアメド』(Telliamed)で自らの考えを示している(本のタイトルはド・マイエ(de Maillet)を逆から読んだもの)。それは、昔の地球は海で覆われていて、その水が徐々に減少していったというものである。そしてド・マイエは、水が減少するには50万年の時間を要すると記し、地球の年齢を20億年と推定した。しかしド・マイエの主張は受け入れられなかった。それは、同書には、男女は雄の人魚と雌の人魚が姿を変えたものだ、などといった荒唐無稽な主張も書かれていたことも原因と考えられている。※1
フランスの博物学者ジョルジュ=ルイ・ルクレール・ド・ビュフォンは、太陽に彗星が衝突して、その時に飛び出した物質が地球になったという考えを持っていた。そこで、実際に鉄球を熱して冷却時間を計り、地球の大きさの鉄球が現在の温度まで下がるには9万6670年と132日かかるという結果を得た。しかし地球は鉄球ではないため、次に「ガラス、砂岩、硬石灰石、大理石および鉄分を含んだ物質」を考えた。さらに、地球は冷えている間にも太陽や月からの熱の影響を受けるため、それも考慮に入れなければならない。こうしてビュフォンは150ページにわたる計算の結果、地球の年齢を7万4832年と導き出した(1778年『自然の諸時期』)。地球の年齢は6000年という考えが一般的だった当時の神学者にとっては、受け入れがたいものだった。ビュフォンの研究はジョゼフ・フーリエによって発展された。フーリエは熱伝導方程式を作り、地球が冷えるまでの年月を計算しようとした。フーリエによる計算結果は残されていないが、実際にフーリエの式から地球の年齢を求めると1億年という数字が得られる。※1
18世紀後半、地質学の世界ではアブラハム・ゴットロープ・ウェルナーの水成説(ネプチュニズム:海神ネプチューンに由来)が知られていた。これは、地球はかつて大洋に覆われていて、その時に海底で今の地形が形づくられ(岩石はすべて海洋の底に堆積した鉱物から形成。火山もその堆積した鉱物から石炭や黄鉄鉱が燃焼した結果)、やがて水が引いて大陸となったという説である(フンボルトはヴェルナーの弟子だった。最終的には水成説は放棄)。「示準化石」(特定の地質時代のみ存在した化石で、地層の形成年代を特定するために使用。アンモナイトは中世代の示準化石)の概念を導入するなど地層と化石の関係を重視。※1
ゲーテは、火成説が急激で激しい火山活動を強調することに抵抗し、穏やかな水の作用による地球の形成を好んだ。彼は、火成説がフランス革命のような暴力的な変化を正当化するものと見なしたため、水成説を支持した(そのためかゲーテは化石を自然の歴史を解明する手がかりとして重視。特に厚皮動物の化石について研究し、絶滅種である可能性を探求)。また、ゲーテは玄武岩の成因についても、火山論者と水成論者を調和させるための和解案を提示した。彼は、単純な水成論には疑問を感じつつも、自然の秩序を理解するための新たな視点を模索していた。このように、ゲーテは水成説を支持しつつも、自然の複雑さを理解するための多様な視点を探求した(またゲーテとフンボルトは1790年代後半から1800年代初頭にかけて頻繁に意見交換をした。互いにイェーナ・サークルのメンバー)。ゲーテは自然自然全体を統一的・哲学的に理解しようとして化石や現生生物の骨格を比較し「原型」という概念で進化や変化を自然の必然的な帰結と捉えた(フンボルトも自然界を統一的なシステムと捉え、自然を「一つの生命」として理解し、すべての要素が相互に関連し合っていると考えた)。
ジェームズ・ハットンは1785年にエディンバラ王立協会で発表した論文でこの水成説を否定するとともに、自説を披露した。それは、地球内部の熱によって地面が押し上げられ、それが海面から上に出て陸地となったというもので、火成説と呼ばれている。花崗岩は水中で堆積によってできたのではなく、マグマが冷えて固まったものである。そして陸地はやがて浸食作用を受ける。ハットンはここで時間について着目した。現在のような地層が見られるということは、地球は現在まで浸食と隆起を何度も繰り返してきたということである。それだけの作用が起きる年月というのは非常に長く、人間の観察できる範囲を超えている。「したがって、人間が観察できるかぎりにおいて、世界に始まりはなく、終わりもない」。ハットンの説は、地球の年齢を6000年とする、当時主流だった考えとは明らかに相反するものであった。ハットンはその後、シッカーポイントの観測により自説が正しいことを確かめ、1795年には自らの理論を著書『地球の理論』としてまとめたが、この理論はハットン存命中には広く伝わらなかった。しかし1802年、同僚のジョン・プレイフェアはハットンの理論をまとめた『ハットンの地球理論の解説』を出版し、ジェームズ・ハットン(英語版)は1804年から1805年にかけて、実験によってハットンの理論の正しさを証明した。そして、チャールズ・ライエルは実地での観測などによりハットンと同じ考えを抱くに至り、1830年、著書『地質学原理(英語版)』を出版した。同書では、地球の年齢は測り知れないほど古いということが記されている。※1ライエルの影響を受けたジョン・フィリップスがガンジス川の堆積速度を基に、地球の年齢を約9600万年と推定した記録(1860年)がある。ライエルは支持しつつも正確な年齢には慎重な姿勢を取っていた。
1859年、ダーウィンは『種の起源』初版で、地球の年齢を少なくとも3億年以上と推定。彼の推定は、当時の一般的な地球の年齢の見解(数千年)とは大きく異なっていた。海岸や川岸の土砂の堆積速度から、地形が形成されるのに数億年かかることを推測した。これは、当時の地質学者が化石や岩石の年代を正確に測定する技術がなかったため、地形の変化速度を観察することで地球の年齢を推定する方法を取ったため。
具体的なデータ源は、イギリス南部のウィールド地方における地質学的観察による。彼はこの地域の広大な谷(森林地帯)が海の波による浸食で形成されたと仮定し、その浸食速度を基に必要な時間を計算した。
ケルヴィン卿が熱力学を用いて地球の年齢を2000万年から4億年(具体的には9800万年と示したが不確定要素を考慮すると)計算し、ダーウィンの推定は批判を受けた。これによりダーウィンが『種の起源』第3版以降でこの記述を削除している(但し、現在は約46億年とされているため事実はダーウィンの方が近かった)。ダーウィンの推定が批判される理由は、当時の物理学的根拠に基づくケルビンの推定と比較して、地質学的観察のみに頼ったものであったため。特に、ケルビン卿の計算は数学的に健全とされていましたが、ダーウィンの推定はより主観的で、具体的な計算方法が不明確であったため、批判を受けた。
トムソンは1862年の論文で、斉一説に次のように反論した。原初の地球は今よりももっと熱い星だった。したがって地球の火山活動なども昔の方が活発であるはずで、現在と同じ活動が過去にも同じ規模で繰り返されたとするのは不適切である。ライエルは『地質学原理』において、地球内部では化学反応によって熱が生み出され、その熱による熱電流によって化合物が分解され、それがまた化学反応して熱に変わるという工程が繰り返されると主張しているが、それは永久運動であって熱力学の基本法則に反する。そしてトムソンは同論文で、具体的に地球の年齢を計算した。方法は、地球が冷却されるまでの時間を求めるというものである。計算の結果、地球の年齢を9800万年、不確定要素を考慮に入れると2000万年から4億年の間と見積もった。※1ドイツの物理学者ヘルマン・ヘルムホルツもトムソンの意見を援護している。1897年にはトムソンは2400万年としている。
時を経て20世紀中頃の放射年代測定技術の発展により、隕石や月の岩石の放射性同位体を用いた年代測定が進み、「約46億年」という推定が確立。
※1…https://www.weblio.jp/content/%E5%9C%B0%E7%90%83%E3%81%AE%E5%B9%B4%E9%BD%A2