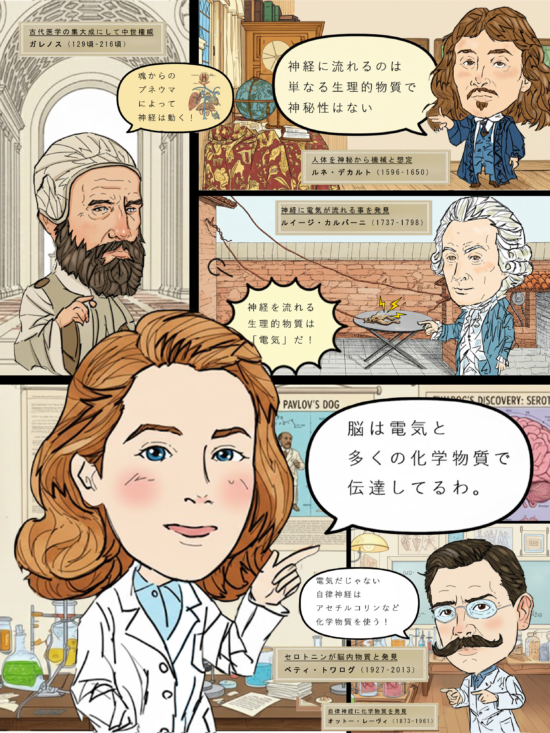稲荷神社は、京都市伏見区にある伏見稲荷大社を総本宮として、全国に約3万社存在する日本で最も普及した神社。
[特徴]
主祭神は「宇迦之御魂大神(うかのみたまのおおかみ)」で、五穀豊穣や農業の守護神として信仰されてきた。稲荷とは「稲成り」(稲が実る)や「稲を荷なう」などが由来。
狐は稲荷神の使いとされている。稲荷信仰と狐が結びついた理由として、狐が農作物荒らしたり蚕の天敵であるネズミを退治するため、農業や養蚕を守るということからという説がある。
[柳田国男の稲荷信仰論]
柳田は稲荷信仰を日本人の生活文化や精神性の中核と捉え、特に農耕儀礼や商業活動との関係を分析した。『山宮考』(1947年)では稲荷神社の起源が山岳信仰(山そのものが神聖視)にあることを指摘し、派生して農耕社会で田の神として崇めあれるようになった過程を論じる。
■①奈良時代~稲荷信仰の始まり~■
総本宮である伏見稲荷大社は平城京遷都翌年の711年(和銅4年)に創建。秦伊侶具が元明天皇の勅命を受けて京都・稲荷山の三ヶ峰に三柱の神(父・佐田彦命と母・大宮能売命と娘・宇迦之御魂大神)を祀った事から。稲荷山は古来より神奈備(かんなび)の山として崇められており、神をなびき寄せる山として信仰の対象だった。この辺りが柳田國男がいう稲荷神社の起源が山岳信仰とした事と関係しているのだろう。
ただし祀られた宇迦之御魂大神は『古事記』では須佐之男命神と大市比売命の子とされ、『日本書紀』では伊邪那岐と伊邪那美が飢えた際に生まれた神とされているため、この三柱の神霊構造は「稲荷信仰」独自の考え方。宇迦之御魂命のウカ(宇迦)は穀物や食物を意味し、宇迦之御(倉稲)魂命は稲の精霊や生命力を象徴。
そして伊侶具が祀ったのが2月の初午(十二支を12日ごとに割り当てる方法での「午」)の日だったため、稲荷神社では初午祭が行れる。初午は農業が始まる時期(春の訪れ)と重なることから、豊作を願う意味も込められている。
[秦氏一族]
伏見稲荷大社創設に貢献した秦伊侶具の一族である秦氏は新羅系の渡来人(他には橘氏、阿刀氏など)で、5世紀頃に朝鮮半島から渡来し、農業技術や水利工学、製鉄などの先進的な技術を日本にもたらした。その為、稲荷信仰はご利益が秦一族の貢献と関係している面があり、五穀豊穣、蚕織などのご利益で人々に信仰される。また、秦氏は朝廷や豪族に重用され、その影響力を背景に稲荷信仰が全国へと広がった。
■②平安時代~空海の神仏習合~■
空海により稲荷信仰は仏教と習合し、空海が習合した真言密教的要素である「荼枳尼天」は戦国武将に信仰された。
[空海の神仏習合]
空海は、遣唐使として帰国し806年に博多に帰着した際(その後大宰府に行き1年間留まる)、稲荷大神のお告げを受ける(博多区古門戸町の沖濱稲荷神社に弘法大師堂として共存)。高野山で仏教の教えを広く伝える本拠を開くように導かれたという伝承がある。
その後、『稲荷大明神流記』では紀州国の熊野で修行していた空海(810~824年頃)が、田辺の宿で常人とは思えない老翁(稲荷神)に出会い、その老翁は「自分は(以前そなたにあった事のある)神である。そなたには威徳がある。私とともに修行して弟子となるがよい」と伝えたという。しかし空海は「密教を広めたいという願いがあります。あなたは仏法でそれを守ってくださるようお願いします。…(東)寺でお待ちしておりますので、必ずお越しください」と約束。823年、空海は嵯峨天皇から東寺を賜り、稲荷神が東寺を訪ねた事から空海はもてなしたという。このようにして稲荷神と真言密教が融合した。
[荼枳尼天と稲荷神の習合]
稲荷神社の狐で巻物を加えている理由の一つとして、この空海が神仏習合した仏教経典、特に空海が中国密教から取り入れた荼枳尼天秘法であるともいわれる。
荼枳尼天(だきにてん)とは、古代インドの「ダーキニー」(Ḍākinī)という夜叉(鬼神)が起源。元々は人肉を食べる恐ろしい存在でしたが、大日如来の説法を受けて仏教の善神となる。荼枳尼天は狐を眷属としているため、同じく狐を使いとする稲荷信仰と融合した。
荼枳尼天秘法は、荼枳尼天が「どんな願いも叶える力を持つ」とされ、個人の願望成就や運命好転を目的とする。そのため万能の願望成就の力を持つ存在として崇められた。荼枳尼天と結びつくことで、稲荷神が農業神から商業全般を守護する万能神へと発展していった。
■③戦国時代~戦国武将の稲荷信仰~■
荼枳尼天秘法では、特定の真言や曼荼羅を用いた修行が行われる。これには強力な霊的エネルギーが宿るとされ、戦国武将や貴族も利用した記録がある。
荼枳尼天は、強力な神通力を持つ護法神として知られ、敵を打ち負かす「怨敵調伏」の力があるとされ、戦国時代の武将にとって、この力は非常に魅力的だった。また、「即効性のある神」として知られ、祈願すれば速やかに結果が現れると信じられていたため、短期間で成果を求める戦国武将たちに支持された。
上杉謙信の兜の前立ては、荼枳尼天を含む五つの神仏の要素を融合した飯縄権現像が使用されたりしている。
織田信長や徳川家康は天下統一のために荼枳尼天を信仰したとされる。ちなみに、関東周辺に稲荷神社が多いのは、徳川家康が天下平定の恩に報いる為に江戸の周辺に多くの稲荷神社を寄進したためとも。
1572~1573年に武田信玄の西上作戦において、武田信玄の体調不良が原因で豊川稲荷のある地域直前で進軍がとまったことから、徳川家康は「豊川稲荷、荼枳尼天の神通力が信玄を追い払ってくれた」と感謝し、家康の荼枳尼天への親交が深まったという逸話もある。
■④江戸時代~遊郭と稲荷神社~■
江戸時代以降は稲荷神社は商売繁盛や家内安全、交通安全などのご利益でも知られている。
商売繁盛の関係から遊郭の近くにつられることも多く、代表的な例として吉原では四隅に配置されていた。特に遊郭から出れない遊女たちにとって重要な信仰の場だった。
■⑤明治時代~南方熊楠と稲荷神社~■
南方熊楠は稲荷信仰を含む日本のアミニズム的な宗教観に注目し、自然と人間の共生を重視した。彼は稲荷神社が地域住民にとって霊的な拠り所であり、自然環境と密接に結びついている点を評価。
1914年、熊楠が住んでいる和歌山県田辺市近郊の伊作田稲荷神社の森が、明治政府が勧めた神社合祀政策により伐採されそうになった際、「伐採は祟りを招く」と警告し、抗議運動を展開。熊楠は伊作田稲荷神社のコジイ(ブナ科シイ属、照葉樹林の代表的な樹種、ドングリをつける)を中心とした豊かな自然環境を持ち、熊楠はその生態系の重要性を強調した。この稲荷神社の森林を「本邦希有の珍品」と評価し、植物学会のために保護すべきだと主張。
熊楠は1905年頃(熊野勝浦から田辺に移住した翌年頃)から稲荷神社で植物採集を行っており、ムギラン、カヤラン、ヨウラクラン、フウランなど珍しい着生植物を発見し、当時の植物研究家から注目されていた。1906年頃から政府の「一町村一神社」を標準とする神社合祀政策が推進されはじめられ、和歌山県では特に強制的に合祀が勧められた。南方熊楠は1909年頃(1908年第二次桂内閣において内務大臣に平田東助が就任すると厳しくなる)から本格的に反対運動を開始。
単なる宗教的な観点からだけでなく、環境保護、文化保存、地域社会の維持など、多角的な視点から展開された先進的な社会運動だった。神社の森(鎮守の森)が自然環境保護に重要な役割を果たしていると主張。特に田辺湾の神島など、貴重な自然環境の保護に尽力した。その中の一環として稲荷神社があったと考えられる。
| 【目次】 |
| ■①稲荷信仰の始まり~伏見稲荷大社と秦氏~■ [秦氏と宇迦之御魂大神] [秦氏一族] ■②平安時代から戦国時代~空海の神仏習合と家康・信長の信仰~■ [空海の神仏習合] [荼枳尼天と稲荷神の習合] [戦国武将との関係] ■③江戸時代:商売との親和性■ ■④明治時代~南方熊楠と稲荷神社~■ |
稲荷神社は、京都市伏見区にある伏見稲荷大社を総本宮として、全国に約3万社存在する日本で最も普及した神社。
[特徴]
主祭神は「宇迦之御魂大神(うかのみたまのおおかみ)」で、五穀豊穣や農業の守護神として信仰されてきた。稲荷とは「稲成り」(稲が実る)や「稲を荷なう」などが由来。詳しくは下記の伏見稲荷大社創建と大きく関係している。
狐は稲荷神の使いとされている。稲荷信仰と狐が結びついた理由として、稲荷神(宇迦之御魂大神)の別名「御饌津神(みけつのかみ:食物を司る神)」が狐の古名「ケツ」と通じだ事からとも。また狐は春になると山から里に降りる習性があるので、豊かな実りをもたらす神の使いと考えられたという説や尻尾が稲穂に似ていることからとも。他には狐が、農作物荒らしたり蚕の天敵であるネズミを退治するため、農業や養蚕を守るということからという説もある。鍵をくわえた狐像があるが、「米倉の鍵」を表し、穀物や財産を守る象徴と解釈する説もある。また狐の好物として油揚げがあるのは、かつて畑を荒らすネズミを捕らえる狐への感謝として、ネズミを模した油揚げ(畑の肉)を供えたという説がある。
[柳田国男と稲荷信仰]
柳田國男は『遠野物語』(1910年)などで地方の民間信仰を記録し、その中で『山宮考』で稲荷信仰も取り上げている。柳田は稲荷信仰を日本人の生活文化や精神性の中核と捉え、特に農耕儀礼や商業活動との関係を分析した。彼は稲荷神が地域ごとに異なる形で信仰されている点に注目し、多様性を強調した。稲荷神社が全国に広まる過程や、その多様な形態(農業神、商業神、家庭の守護神など)に注目し、日本人の生活文化との関係性を分析した。
『山宮考』(1947年)では稲荷神社の起源が山岳信仰(山そのものが神聖視)にあることを指摘し、派生して農耕社会で田の神として崇めあれるようになった過程を論じる。
柳田国男の視点とは違うが、歴史軸から多方向への展開を読んでいく。
■①稲荷信仰の始まり~伏見稲荷大社と秦氏~■
総本宮である伏見稲荷大社は711年(和銅4年)に創建。渡来人である秦氏が稲荷神を祀ったことから始まり、大陸由来の稲作文化と融合して日本各地に広がる。
[秦氏と宇迦之御魂大神]
具体的な創建は711年に秦伊侶具が元明天皇(中臣鎌足の次男である藤原不比等と共に710年に平城京を作る)の勅命を受けて京都・稲荷山の三ヶ峰に三柱の神(宇迦之御(倉稲)魂命・佐田彦命・大宮能売命を一ヶ峰~三ヶ峰にそれぞれ)を祀ったことから。三柱の神は、父(佐田彦命)と母(大宮能売命)と聖霊(中心:娘:宇迦之御魂大神)という三柱の神霊構造で稲荷信仰では考える。ただし宇迦之御魂大神は『古事記』では須佐之男命神と大市比売命の子とされ、『日本書紀』では伊邪那岐と伊邪那美が飢えた際に生まれた神とされているため、三柱の神は「稲荷信仰」独自の考え方。宇迦之御魂命のウカ(宇迦)は穀物や食物を意味し、宇迦之御(倉稲)魂命は稲の精霊や生命力を象徴。
そして秦伊呂具が稲を積んで富裕になった後、餅を弓矢の的にすると白鳥となって飛び去り、山の峰に稲が生えたことから「伊禰奈利(いねなり)」と呼ばれるようになった(伊(禰)奈利神を祀った)とされる(『山城国風土記』)。この三柱の神が同様の性質を持つことから統合し、さらに「伊(禰)奈利」神と同様の性質を持つことから「宇迦之御魂大神」が主祭神となる。
また、711年、伏見稲荷大社がある稲荷山(三ヶ峰)に稲荷大神が2月の初午(十二支を12日ごとに割り当てる方法での「午」)の日に出現した(伊侶具が伊奈利神を鎮座した)ことに由来して、稲荷神社では初午祭が行れる。初午は農業が始まる時期(春の訪れ)と重なることから、豊作を願う意味も込められている。稲荷山は古来より神奈備(かんなび)の山として崇められており、神をなびき寄せる山として信仰の対象だった。円錐形の山は特に神聖視され、雷神を招き降ろし、豊かな実りをもたらすと考えられていた。
[秦氏一族]
伏見稲荷大社創設に貢献した秦伊侶具の一族である秦氏は新羅系の渡来人(他には橘氏、阿刀氏など)で、5世紀頃に朝鮮半島から渡来し、農業技術や水利工学、製鉄などの先進的な技術を日本にもたらした。京都の山背国(現・京都市伏見区)を拠点とし、地域開発を進める中で稲荷神を祀る信仰を形成した。
秦氏は渡来人として高度な農業技術を持っており、未開拓だった山背の盆地を開墾し、治水・農業・養蚕を行った。上記の「稲荷(伊禰奈利)」の名前由来である伊侶具の伝説も、稲作によって富を築いたということに由来する。その為、稲荷信仰は五穀豊穣、蚕織などのご利益で人々に信仰される。
また、秦氏は朝廷や豪族に重用され、その影響力を背景に稲荷信仰が全国へと広がった。この過程で、稲荷神は農業神から商売繁盛や家内安全など多様なご利益を持つ神として発展した。
仏教の普及にも貢献していて、秦氏一族の秦河勝は聖徳太子の側近として、仏教普及に貢献。聖徳太子から仏像を賜り、京都に広隆寺を創建。他にも秦氏一族は財力を活かして多くの神社を建立していた。また空海の母方は阿刀氏で同じ新羅系であるため秦氏と関連があったとされ、空海の仏教学習や唐への留学を支援した可能性もある(阿刀氏は法相宗の発展に貢献し、皇族の教育にも関わる)。更に虚空蔵菩薩信仰(空海も修行時代信仰)と関りが深い。日本の宗教文化、神社神道と仏教の融合に大きな影響をあたえたとされる。
■②平安時代から戦国時代~空海の神仏習合と家康・信長の信仰~■
空海により稲荷信仰は仏教と習合し、この仏教的要素である荼枳尼天は戦国武将に信仰された。
[空海の神仏習合]
この荼枳尼天と稲荷神の習合は空海の功績が大きく、稲荷信仰に密教的な要素が加わり、日本各地に広まる。
荼枳尼天は中国密教において主に呪術的な儀礼で用いられていたため、中国密教を学んだ空海は、荼枳尼天を真言密教に取り入れていた。
空海は、遣唐使として帰国した際、806年に博多に帰着した際(その後大宰府に行き1年間留まる)、稲荷大神のお告げを受ける(博多区古門戸町の沖濱稲荷神社に弘法大師堂として共存)。高野山で仏教の教えを広く伝える本拠を開くように導かれたという伝承がある。
その後、『稲荷大明神流記』(東寺に伝わる文献)では紀州国の熊野で修行していた空海(810~824年頃)が、田辺の宿で常人とは思えない老翁(稲荷神、『稲荷大明神縁起』では竜頭太とも呼ばれる)に出会い、その老翁は「自分は(以前そなたにあった事のある)神である。そなたには威徳がある。私とともに修行して弟子となるがよい」と伝えたという。しかし空海は「密教を広めたいという願いがあります。あなたは仏法でそれを守ってくださるようお願いします。…(東)寺でお待ちしておりますので、必ずお越しください」と約束。823年、空海は東寺を賜り、稲荷神が空海を訪ねた事からもてなしたという。熊野は古代から山岳修験道や浄土思想と結びついており、稲荷信仰もその一部として登場した可能性がある。老翁の竜頭太は姓を「荷田氏」(稲を担ぐという意味が込められている)であり農耕神である稲荷信仰との関連が見られる。
つまり稲荷山の山頂に祀られていた稲荷神を、京都の東寺(教王護国寺)の鎮守神として祀る(おそらく稲荷神と真言密教が融合したということ)。東寺はもともと794年に桓武天皇が平安京を造営する際国家鎮護のために「東寺」(平安京の正門である羅生門の東側)と「西寺」を設置したことが始まりで、823年に空海が嵯峨天皇から託された真言密教の中心地であった。それから稲荷信仰は東寺を拠点に広まり、農業神から商業や工業など幅広い分野での守護神へと発展した。
[荼枳尼天と稲荷神の習合]
稲荷神社の狐で巻物を加えている理由の一つとして神仏習合の影響があるともいわれる。巻物を仏教経典、特に荼枳尼天秘法とすることもあるという。空海が荼枳尼天と稲荷神を集合させたという。空海が真言密教に取り入れ、稲荷信仰と融合させて庶民にも広がったという。
荼枳尼天(だきにてん)とは、古代インドの「ダーキニー」(Ḍākinī)という夜叉(鬼神)が起源。元々は人肉を食べる恐ろしい存在でしたが、大日如来の説法を受けて仏教の善神となる。荼枳尼天は狐を眷属としているため、稲荷信仰と融合した。狐は荼枳尼天の使いとして、人間の願いや祈りを神仏へ届ける役割を果たす。
荼枳尼天秘法は、荼枳尼天が「どんな願いも叶える力を持つ」とされ、個人の願望成就や運命好転を目的とする。そのため万能の願望成就の力を持つ存在として崇められた。荼枳尼天と結びつくことで、稲荷神が農業神から商業全般を守護する万能神へと発展していった。
ただし、明治政府による神仏分離政策の影響で多くの稲荷神社では荼枳尼天が排除され、代わりに宇迦之御魂神が祭神とされるようになったということも起きている。
[戦国武将との関係]
荼枳尼天秘法では、特定の真言や曼荼羅を用いた修行が行われる。これには強力な霊的エネルギーが宿るとされ、戦国武将や貴族も利用した記録がある。
荼枳尼天は、強力な神通力を持つ護法神として知られ、敵を打ち負かす「怨敵調伏」の力があるとされ、戦国時代の武将にとって、この力は非常に魅力的だった。また、「即効性のある神」として知られ、祈願すれば速やかに結果が現れると信じられていたため、短期間で成果を求める戦国武将たちに支持された。
上杉謙信の兜の前立ては、荼枳尼天を含む五つの神仏の要素を融合した飯縄権現像が使用されたりしている。
織田信長や徳川家康は天下統一のために荼枳尼天を信仰したとされる。ちなみに、関東周辺に稲荷神社が多いのは、徳川家康が天下平定の恩に報いる為に江戸の周辺に多くの稲荷神社を寄進したためとも。
1572~1573年に武田信玄の西上作戦において、武田信玄の体調不良が原因で豊川稲荷のある地域直前で進軍がとまったことから、徳川家康は「豊川稲荷、荼枳尼天の神通力が信玄を追い払ってくれた」と感謝し、家康の荼枳尼天への親交が深まったという逸話があります。このとき、家康は自身の領地(遠江国と三河国)を守りつつ、同盟者である織田信長のために戦う立場にあったが、経験と兵力の面で不利な状況(三方ヶ原の戦いでは敗れている)に置かれていた。
五大稲荷の一つとされることもある長野県鼻顔稲荷神社も1558~1569年に出来ているため、荼枳尼天信仰と関係があったのかも知れない。
■③江戸時代:商売との親和性■
江戸時代以降は稲荷神社は商売繁盛や家内安全、交通安全などのご利益でも知られている。
商売繁盛の関係から遊郭の近くにつられることも多く、代表的な例として吉原では四隅に配置されていた。特に遊郭から出れない遊女たちにとって重要な信仰の場だった。
長野県佐久市の鼻顔稲荷神社も湯川を挟んで「信州の吉原」とも呼ばれた岩村田遊郭があり、遊郭の繁栄と関係があるのかも知れない。
■④明治時代~南方熊楠と稲荷神社~■
南方熊楠は稲荷信仰を含む日本のアミニズム的な宗教観に注目し、自然と人間の共生を重視した。彼は稲荷神社が地域住民にとって霊的な拠り所であり、自然環境と密接に結びついている点を評価。
1914年、熊楠が住んでいる和歌山県田辺市近郊の伊作田稲荷神社の森が、明治政府が勧めた神社合祀政策により伐採されそうになった際、「伐採は祟りを招く」と警告し、抗議運動を展開。熊楠は伊作田稲荷神社のコジイ(ブナ科シイ属、照葉樹林の代表的な樹種、ドングリをつける)を中心とした豊かな自然環境を持ち、熊楠はその生態系の重要性を強調した。この稲荷神社の森林を「本邦希有の珍品」と評価し、植物学会のために保護すべきだと主張。
熊楠は1905年頃(熊野勝浦から田辺に移住した翌年頃)から稲荷神社で植物採集を行っており、ムギラン、カヤラン、ヨウラクラン、フウランなど珍しい着生植物を発見し、当時の植物研究家から注目されていた。1906年頃から政府の「一町村一神社」を標準とする神社合祀政策が推進されはじめられ、和歌山県では特に強制的に合祀が勧められた。南方熊楠は1909年頃(1908年第二次桂内閣において内務大臣に平田東助が就任すると厳しくなる)から本格的に反対運動を開始。1910年に反対運動の一環で、田辺中学校講堂で行われていた夏期講習会(本多静六が講師)閉会式で神社合祀推進者県吏田村が来るということで、信玄袋を投げつけ18日間拘留されている。拘留後、熊楠は牟婁新報に「人魚の話」をのせて警官に攻撃する。そのとき牟婁新報の社長・毛利柴庵(熊楠の神社合祀反対運動を支援)は、大逆事件に関連して少し前に家宅捜査を受けている(1905~1906年頃菅野スガと荒畑寒村が記者として働いていた)。
単なる宗教的な観点からだけでなく、環境保護、文化保存、地域社会の維持など、多角的な視点から展開された先進的な社会運動だった。神社の森(鎮守の森)が自然環境保護に重要な役割を果たしていると主張。特に田辺湾の神島など、貴重な自然環境の保護に尽力した。その中の一環として稲荷神社があったと考えられる。