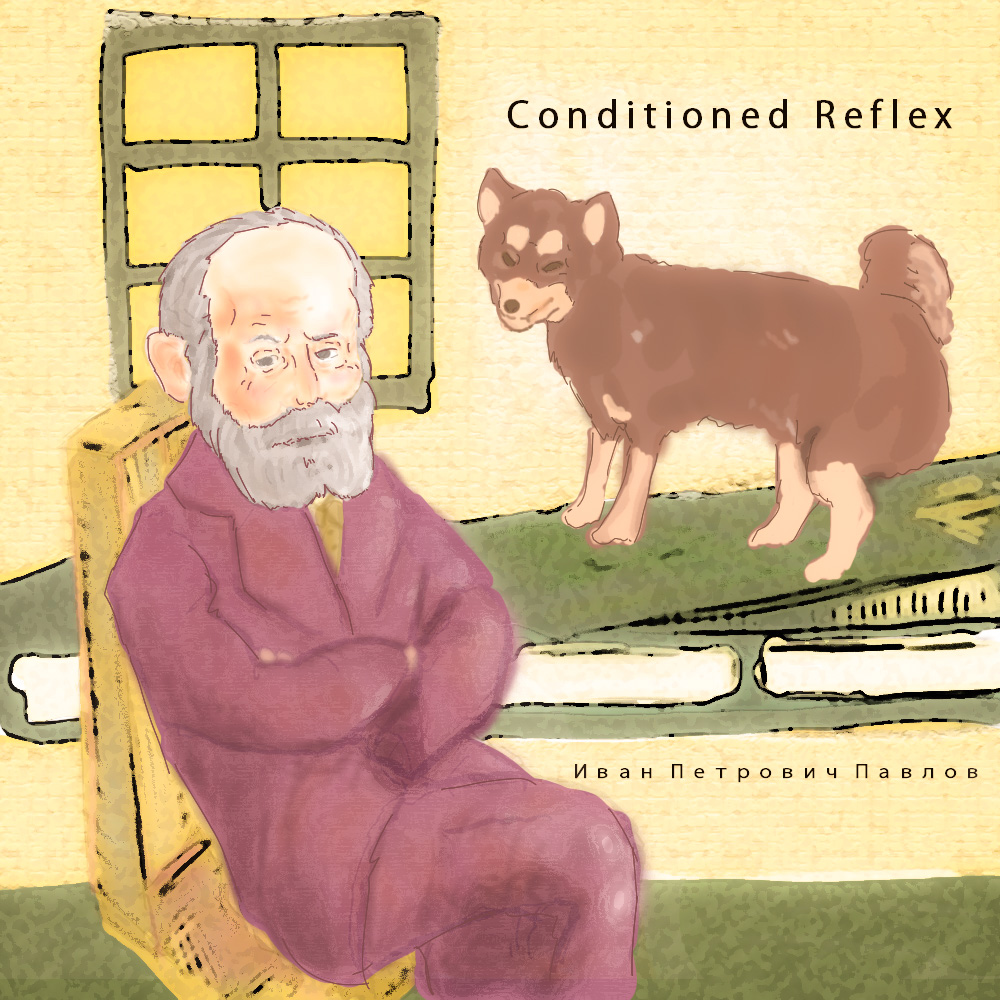第一次世界大戦中にロシアは「ラスプーチン」という謎の人物が政治に携わり、更に「レーニン」の登場によってロシア革命が成されました。その2つのキーワードを第一次世界大戦の進行と絡めて論じていきたいと思います。
またロシア革命によって生活に困窮した「パブロフの犬」の発見者は、こちらは哲学の世界にどのように影響をしたのかもおまけとして論じていきます。
| 目次 |
| 1章 第一次世界大戦とロシア ⅰラスプーチン ■➀ラスプーチンのロシア皇帝との接点■■②ラスプーチンの影響力の拡大■■③ラスプーチンの最後までの道筋■ 2章 第一次世界大戦とロシア ⅱレーニン ■➀レーニンと第一次世界大戦■■②二月革命とボリシェヴィキの結びつき■■③ケレンスキー攻勢と七月蜂起■ 3章 パブロフの犬とレーニンとデカルト ■➀パブロフとレーニンの交友■■②条件反射と心身二元論■ |
1章・第一次世界大戦とロシア➀ラスプーチン

サラエボ事件からセルビアの支援として第一次世界大戦に参加したロシアですが、戦争が長引き大戦中にロシア革命が起ってしまいます。
ラスプーチンの登場から終わりまでも、この第一次世界大戦と大きく関係しています。
■➀ラスプーチンのロシア皇帝との接点■
1892年、ラスプーチンは唐突に父親や妻に「巡礼に出る」と言い残して村を出ていきました。啓示を受けたとされ、その後修行僧になり、巡礼の旅に出ました。
そして1904年頃、サンクトペテルブルクに訪れ、人々に病気治療を施して信者を増やし「神の人」と称されるようになりました。
1905年には神秘主義に傾倒していたロシア皇帝のニコライ2世とアレクサンドラ皇后に謁見しました。そして1907年に血友病患者であったアレクセイ皇太子の治療に当たり、祈祷を捧げると症状が改善しました(1899年以降流通し始めた鎮痛薬アスピリンの投与による治療だったとも)。
それによって、皇帝夫婦から絶大な信頼を得ました。
ただし、ラスプーチンを信仰するものと疑いの目でみるものが入り乱れ、必ずしもラスプーチンの処遇は安定したものではありませんでした。
■②ラスプーチンの影響力の拡大■
しかし、1914年6月29日、第一次世界大戦がはじまるサラエボ事件(オーストリア皇太子がセルビアの青年に暗殺された事件)の翌日でもある日、ラスプーチンは帰郷していた自宅で男に襲われ腹部をさされてしまいまうも一命を取りとめました。
この暗殺未遂によってラスプーチンを公然と批判する勢力がいなくなる結果となり、以後ラスプーチンは政治にも影響力を持つようになりました。
その後、サラエボ事件はヨーロッパ諸国を巻き込む戦争となり第一次世界大戦と発展し、セルビアに進行するオーストリア=ハンガリー二重帝国軍がロシアに対して8月6日に宣戦布告すると、ロシアもオーストリア=ハンガリー二重帝国軍に宣戦布告をしています。
そしてロシア軍対オーストリア=ハンガリー二重帝国軍とドイツ軍が主な戦いとなる東部戦線が始まりましたが、ドイツ軍は主に西部戦線に集中し、オーストリア=ハンガリー二重帝国軍はロシアの侵攻経路を見誤り、1914年10月あたりにはオーストリア=ハンガリー二重帝国国境辺りで戦線が膠着しました(主な軍を撃破し、プシェミシル要塞を占領した分、ややロシアが優勢ともみれます)。
その後、1915年4月からオーストリア=ハンガリー二重帝国はドイツ軍の力を借りて「ゴルリッツ突破戦」という西部戦線で使われていた「弾幕射撃」を使った大規模な攻撃を受け、オーストリア=ハンガリー二重帝国とドイツ軍が8月頃には有利になりました(8月にはドイツ軍がワルシャワを占領しロシアの大撤退(Great Retreat)が起こり、ロシア軍は深刻な弾薬・兵器不足に陥り、ロシア国内が混乱し始めました)。
恐らくその関係もあり1915年8月19年にラスプーチンの醜聞を新聞に持ち込もうとする事件などが起こり、ニコライ二世は以後、皇后アレクサンドラとラスプーチンの関係を議論する事を禁止しました。
またニコライ2世は東部戦線を立て直すために自ら戦地に赴く「親征」を行う事にしました。これによって内政はアレクサンドラ皇后が摂り、ラスプーチンが相談役になるという体裁をとるようになりました。
■③ラスプーチンの最後までの道筋■
1915年6月、西部戦線において甚大な被害を受けていたフランスと、イタリア戦線でオーストリア=ハンガリー二重帝国に被害を受けていたイタリアからの要請から、東部戦線においてロシアが大規模な攻勢を仕掛ける「ブルシーロフ攻勢」を行う事になりました。
「ブルシーロフ攻勢」は、ドイツが使っていた「浸透戦術」などを参考にして新たに考え出した戦術を用いた1915年6月から9月の攻勢ですが、少なくとも前半は圧倒的にロシアの優勢となりましたが、後半においてはかなり反撃もされ、総合的には連合国の西部戦線の窮地を救う戦略的勝利とも言えますが、ロシアにとっても損害は大きく、ロシア革命に繋がる要因になっていきます。
戦争が長期化している事と、この「ブルシーロフ攻勢」の損害もあり、国民の不満が増大し、ラスプーチンに対する批判も高まり、貴族の間で再び暗殺計画が持ち上がり、遂にはラスプーチンは1916年12月17日に暗殺されてしまいます。
※参考文献…wikipedia「ラスプーチン」、時空旅人『ロシアとはどういう国か?』2017.4.23三栄書房
第二章・第一次世界大戦とロシア②レーニン

1914年6月サラエボ事件が起こりロシアが介入することで第一次世界大戦に発展しましたが、戦争を続けていく内にロシアにとって大きな損害が生じてきてしまい、ロシア国内ではニコライ2世の王朝に対する批判が強くなり、1916年12月にはラスプーチンが暗殺される事態となってしまいました。その後、ロシア国内では王朝を打倒する社会革命が起っているのですが、そこでレーニンが登場し始めてソヴィエト連邦が成立する「十月革命」に繋がっていきます。
今回は、レーニンの第一次世界大戦に対する考えと、「二月革命」から「十月革命」の間のレーニンを中心に論じていこうと思います。
■➀レーニンと第一次世界大戦■
1895年、レーニンはサンクトペテルブルクの全てのマルクス主義労働者グループを統合して「労働者階級解放闘争同盟」を結成しました。しかし、逮捕され扇動罪に問われ、1年の収監と3年の流刑を経て、1900年から他国へ亡命していました。
1914年7月末にサラエボ事件から第一次世界大戦に発展した際、レーニンは「帝国主義戦争を内乱に転化せよ」と考えました。
その考えを1916年チューリッヒに移り執筆した『帝国主義の最高段階としての帝国主義』『マルクス主義の戯画と「帝国主義的経済主義」について』の中で深めました。
そして、社会革命というものは、先進国のブルジョワジーに対するプロレタリアートの内乱と、低開発で後進的な被抑圧民族のいくたの民主主義的革命運動(民族解放運動を含む)が結合した時代でしか起こりえないと指摘しました。
更に帝国主義が世界に不均等な発展しかもたらしえないため、それに対決する具体的な革命の形態も多様でなければならないことも述べました。
ただ、レーニンは第一次世界大戦の進展につれて反戦運動が強まり、革命の機運の進むことを疑わなかったようですが、その革命の機運が進む時期がいつになるかまでは予知できていない状態でした。1917年1月22日チューリヒの人民ホールで「血の日曜日」の12周年を記念する集会においては「われわれ老人は、もしかすると、この革命の決定的戦闘まで生きのびられないかもしれません」とも述べているほどです。
そんな中に1917年2月、「二月革命」が起こりました。
■②二月革命とボリシェヴィキの結びつき■
1917年2月、二月革命が起り、首都の権力は実質的に労働者の手に握られ、ニコライ2世のツァーリ政権は打倒され、ニコライ2世は退位しました(ロマノフ王朝の崩壊)。
そして、ロシアは再び結成されたソヴィエト(自然発生的に形成された労働者農民・兵士の評議会、このときは社会革命党とメンシェヴィキが多数を占めてました)と自由主義中心の臨時政府の二重権力状態(構造)で統治されることになりました。
この革命は、かならずしも革命勢力の理論的指導によってもたらされたものではありませんでした。その当時、多くの革命家たちはロシア内で弾圧され流刑地にあった上、レーニン率いるボリシェヴィキは当時弾圧により弱体化しており、ペトログラード(サンクトペテルブルク)に主要な幹部がおらず、二月革命で指導力を発揮する事はできなかったのです。
そんな中、3月にはボリシェヴィキの方針は臨時政府に対する条件付き支持と第一次世界大戦の戦争継続の容認に定まりました。
そして、レーニンは二月革命を祝いロシアへの帰国の意志を固めます。4月3日、ロシアの同盟国たるイギリス、フランスなどの手によって帰国することは(ロシアの政情の不安定にする要因としてレーニンが見られているため)不可能であったので、敵国であるドイツ政府の了解のもと(ドイツにとってはレーニンが帰国する事でロシアに混乱が起きることを期待した)に、いわゆる「封印列車」(ドイツを通過するもののドイツを見ることができないようにしている列車)に乗って帰国します。
帰国後の4月4日にレーニンは、戦争と臨時政府に反対する労働者の集会に参加し、労働者代表ソヴィエトをただ一つの可能な革命政府の形態と評価し、臨時政府の打倒と全権力のソビエトへの意向を主張(パリ・コミューンと同じ型の権力と評価)した「四月のテーゼ」を掲げました。
具体的には、ペトログラードのソヴィエトを支配しているメンシェヴィキと社会革命党がロシア臨時政府に協力していることを批判し、臨時政府はツァーリ(ロマノフ王朝)の政府と同程度に帝国主義的であると定義し、プロレタリア政権を樹立して社会主義社会へ向かうための手段として、ドイツおよびオーストリア=ハンガリーとの即時和平・ソヴィエトへの権力集中・産業と銀行の国有化・国家による土地収用などを提唱しました。
そして、メンシェヴィキはロシアがまだ社会主義社会に移行する段階にたっしていないと考えており、レーニンは誕生したばかりの新共和国を内戦へと導こうと試みていると批判しました。
1917年6月16日に第一回全ロシア・ソヴィエト大会では、822名の代議員の中、社会革命党(エスエル)は285名、メンシェヴィキは248名、ボルシェヴィキは105名とボルシェヴィキはこのときは少数勢力でした。
そんな中、メンシェヴィキの郵便電信大臣ツェレテリが演説で、「現在のロシアには、こちらに政権を引き渡せ、諸君は立ち去って、われわれに席を譲るがよい、と言える政党はありません。」と言い、そのため「当時の不安定なロシアの政情では各政党が協力して挙国一致体制を採るべき」と主張しました。
すると、レーニンは「臨時政府に対して宣戦布告し、ボリシェヴィキが権力をとる用意がある」と臨時政府に対して宣戦布告しました。ただ、このときはあまりレーニンの発言をまわりは本気だと思っていなかったようです。
この大会の結果、挙国一致体制の組織として社会革命党、メンシェヴィキ、ボリシェヴィキ(35名:このときボリシェヴィキはグループの中で意見が割れつつあった)、その他小グループを含めた「全ロシア中央執行委員会」が結成されました。
■③ケレンスキー攻勢と七月蜂起■
6月18日から同盟国から熱望されドイツに対してロシアは大攻勢をしかけることになりました。そして、ケレンスキー攻勢を7月1日(~19日)ロシア軍最後の侵攻として行われます。
一方、このころロシア国内は、凄まじい混乱と暴力に満ちた社会となり、社会秩序そのものが無きに等しい状況に陥っていました。
7月1日ケレンスキー攻勢が行われたとき、ペトログラード(サンクトペテルブルク)の中心にある広場マルソヴォ・ポーレにおいて、全ロシア・ソヴィエト大会はデモを行い始めました。
このデモは、臨時政府側やビルシェヴィキ党中央委員会の想定以上に、ロシア国内では武装政治デモに対する支持が拡大している状況となっていました。
この状況をトロッキーは後に「労働者は戦争と戦争の幻想、偽り、祖国防衛のうそを卒業して、そしていやまや大いなる犠牲と、未開の努力の用意をしていた。」と論じています。また「兵士たちはこの(第一次世界大戦が始まってからの)三年間、意味のない犠牲と、屈辱のすべてを買い戻そうとし、何ものをも惜しまない荒れ狂う憎悪の爆発をもって戦争を吹き飛ばした。…農民は…戦争によって目ざめ、はじめて抑圧者、奴隷所有者、主人たちにむかって、手ごわくまた何ものをも惜しむことなく決着をつけることができそうになっていた」と述べています(『レーニン』トロッキー著より)。
7月16日には「ケレンスキー攻勢」によるロシアの前進は完全に失敗している状況になっていました。
するとペトログラードで一部を前線へ送れという政府命令に抵抗していた機関銃歩兵第一連隊の兵士たちによる自発的なデモが(失敗の顕在化としての7月15日のガデット所属三大臣の辞職をみて)発生しました。さらに他の兵士や工場の労働者もデモへ参加しました。こうして「七月蜂起」が起こりました。
これに対し全ロシア中央執行委員会はデモ禁止令を出しました。一方、デモ隊がボリシェヴィキ党支部にきた際には、ボリシェヴィキは「組織的」で「平和的」を提案しました。
具体的には7月17日に「すべての権力をソヴィエトへ!」というスローガンの下、50万人の労働者、兵士、水兵(クロンシュタット含む)による平和的デモが行われました。
デモ隊はペトログラード・ソヴィエト委員会があるタヴリダ宮殿に行き、その中で全ロシア中央執行委員会は臨時政府との協調的姿勢を示したため、農相チェルノフが群衆によって拘束され、トロッキーによって解放されるという一幕がありました。
そして、レーニンは病気療養中のためフィンランドで静養中であったが、ペトログラードに戻ってきました。このとき、レーニンは平和的手段でなく武力に依らなければ政権をとることはできないが、現状ではボリシェヴィキ側の武力は不足し、かりに武力蜂起に踏み切っても成功しないと考えていました。そのため、来るべき武力蜂起の時に備えるべく、現時点ではボリシェヴィキは平和的なデモによって政府に圧力を加える路線を取らざるを得ないと考えていました。
ただ、血の気の逸った大衆たちからの支持を落とさないように武力蜂起への動きを抑えなければならないとも考えました。またボリシェヴィキが党として武力蜂起への陰謀を指導したという証拠を残してはならない、とも考えました。
そんな中、臨時政府はレーニンがドイツのスパイ(おそらく二月革命の後、帰国する際ドイツの「封印列車」を使ったことに起因した嫌疑)であることを「証明」する文章を見せるという事を行っています。
そんな事もあったため、「七月蜂起」の直後はレーニンは支持を下げますが、10月には支持を集め「十月革命」でレーニンによりソヴィエト政権が成立しました。
その後、ボリシェヴィキ政権は単独でドイツ帝国と講和条約(ブレスト=リトフスク条約)を結んで第一次世界大戦から離脱しました。
ただし、1918年11月17日に第一次世界大戦においてドイツ・オーストリアの敗北に伴い、ロシアが第二次ソビエト・ウクライナ戦争が始まり、これがシベリア出兵へ繋がります。
※参考文献…wikipedia「ソビエト」「4月テーゼ」「レーニン」「七月蜂起」「ケレンスキー攻勢」、時空旅人『ロシアとはどういう国か?』2017.4.23三栄書房、『レーニン』L.トロッキー1972.2.25河出書房新社、『世界の名著レーニン』江口朴郎1966.5.10中央公論
3章・パブロフの犬とレーニンとデカルト

「条件反射」の発見で知られる「パブロフの犬」ですが、この発見はロシア革命が起る時代のもので、そしてその発見は「哲学」の新しい方向性に繋がった要素でもありました。
■➀パブロフとレーニンの交友■
1917年の十月革命でレーニン率いるボルシェビキが政権を握りましたが、その際、ロシアで初めて1904年にノーベル賞を受賞したイワン・パブロフはその賞金を没収されてしまいました。
1920年6月に生活に困窮したパブロフは、ボリシェビキ政権に対し、国外移住の希望を伝える手紙を出しました。すると、レーニンは偉大な化学者の国外移住を避けるために全面支援をし、またレーニン自身パブロフと親交を持つようになりました。
ただし、パブロフは研究費など全面的に支援してもらいましたが、ソヴィエト共産主義に対して不承認と軽蔑を隠そうとはしなかったようです。
一方、レーニンの方は国民の再教育を考えていたため、条件反射の発見は「全世界の労働者階級にとって重大な意義をもつ」と賛辞を与えたようです。パブロフ自身も自身の発見に基づいて教育論まで展開する志向を持っていたようです。
■②条件反射と心身二元論■
パブロフがノーベル生理学・医学賞を受賞したのは消化腺の研究に基づくもののようです。そのような消化生理学に関する研究を行う中で、犬の唾液腺を研究する中で、条件反射を発見したようです。
さて「条件反射」の発見の意味ですが、バートランド・ラッセルは『西洋哲学史』の中で、「心理学は心をより少なく心的なものにしてきた」という中での例として出しています。
もともと反射や条件反射などの心の作用は、哲学の世界で語られていました。
特にデカルトの時代(17世紀)には「心身二元論」という考えで、実験や観察などによって考察を深められる性質のあるものを「物質(身)」と考え、それが難しい「心(精神)」の作用とは別物の性質のもとと考えました。
そのため、前者は「自然科学」によって語られ、後者は「哲学」によって語られてきました(特に「観念連合」というフレームワークで研究されていました)。
ただし、ラッセルによると「心と物質との区別は、長らくの間、妥当な根拠を持つように見えはしたが、その区別は宗教から哲学に流入したものであった」と語っています。
それはデカルト自身も非常に合理的で実験や観察に基づいた真理の探究と数学に基づいた法則の発見を重んじた人間でありましたが、心の問題に関しては神から与えられたものとして、その理性を上手く使う事によって人は啓蒙されると考えていたようなことを示唆しているのだと思います。
確かに、デカルトは『情念論』などにおいては脳の働きによる「思考」を考察して、いわゆる「反射」にあたるような記述もしています。しかし、そのデカルトでさえも確かに脳の「松果体」など器質的な解剖的な側面は論及していますが、そのメカニズムに関しては想像によって描かれたものである側面が強いのだと思います。
一方、パブロフが発見した「条件反射」はデカルトとメカニズム的な部分は似通っている所もありますが、科学的実験によってそのメカニズムを発見したというところがかつての「哲学」で探求されていた時代と一線を引くのだと思います。
ラッセルはこの視座は「明白により多く生理学的なものである」と述べています。
そしてこのパブロフの「条件反射」の発見辺りから科学的実験によって「哲学」から分離した「心理学」が登場し、「心身二元論」によって「物質」と「心」によって分離されていたものが「両極端から物理学と心理学は互いに近づいてきた」(『西洋哲学史』)時代となってきたのだと考える一つのきっかけといえると思います。
※参考文献…Wikipedia「イワン・パブロフ」及び英語版「Ivan Pavlov」、『西洋哲学史・下巻』ラッセル(訳)市井三郎1956.1.25みすず書房