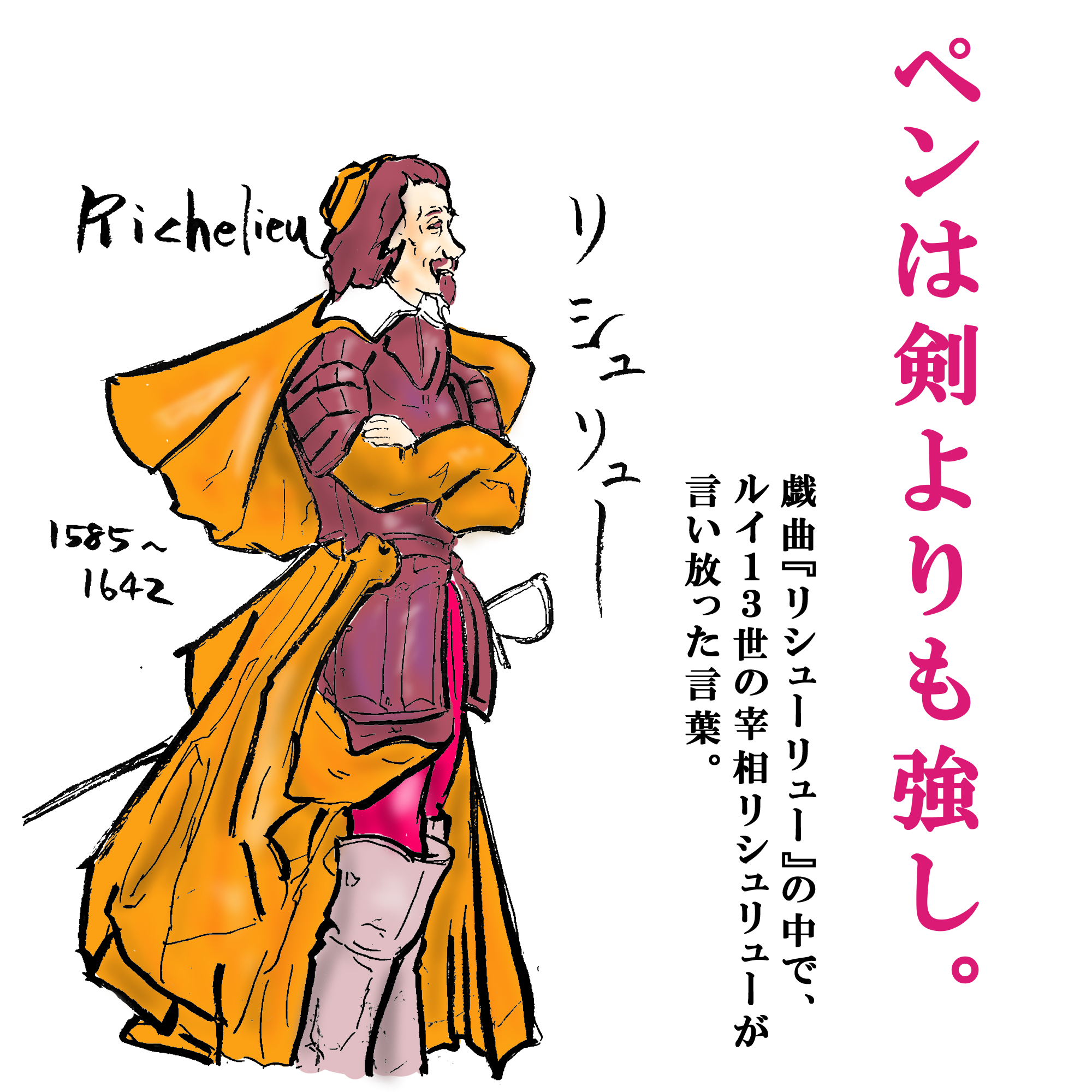三十年戦争にフランスがどのように介入していったか、書いていきたいと思います。
| 1章・三十年戦争の軍事革命 ■①皇帝軍の徴兵戦略■■②スウェーデン軍の常備軍■ 2章・フランスの三十年戦争の参入➀遠因 ■①戦争を指揮する僧侶■■②北イタリアでの争い■ 3章・フランスの三十年戦争の参入②参入 ■①ルーベンスの活躍■■②スウェーデンの参入決断■■③英雄死と泥沼化■■④フランスの参入■ |
1章・三十年戦争の軍事革命

1632年、リュンツェンの会戦において、グフタス・アドルフの率いるスウェーデン軍は皇帝フェルティナンド二世のもと軍を率いるヴァレンタインの大群に対し、見事に勝利しました。
この戦いは三十年戦争の第三ラウンドのクライマックスですが、この皇帝軍とスウェーデン軍両者の軍隊は、共に革新的な方法で作られた軍隊でした。
■①皇帝軍の徴兵戦略■
当時は槍や火縄銃が中心で、剣が幅を利かせていた時代で、騎士の活躍もまだ大きかったようです。更に、傭兵が中心で軍使を立てて宣戦する名残も残っていたようです。
その中で、皇帝側のヴァレンシュタインは、民間投資家に大金を出してもらい、自分の領地のマニュファクチュアで武器や軍服など軍に必要なものは作り上げ、武器商人の納期に左右されることなく軍の装備を揃え、さらに装備の統一を行いました。また、皇帝の権力を縦に略奪ともいえるほどの軍税を占領地で取り立て資金を回収し、傭兵の補充から戦力化まで機能的に行うシステムを作り、雪だるま式に大軍を揃えました。
この大軍を揃えるシステムによってデンマーク王クリスチャン4世をドイツから放逐したのが三十年戦争の第二ラウンドです(第一ラウンドは、プロテスタント諸侯がプファルツ公をボヘミア王に立てて、皇帝フェリペ二世が攻撃を仕掛け、皇帝が勝利するものです)。
■②スウェーデン軍の常備軍■
一方、グフタス・アドルフは、徳川家康の時代に朱印状を交付してもらうべくオランダ東会社が「国王」という名目で用いたオラニエ公マウリッツの軍制改革を完成させたものと言われています。
マウリッツは、軍事訓練の徹底したマニュアル化をすることで「軍事改革」を起こしており、さらにそれらの方法を書籍化したり教えたりもしていました。そしてそのマウリッツの教えを受けたのがグフタス・アドルフです。
グフタス・アドルフはヨーロッパ近代最初の徴兵制をスウェーデンで敷いて、その常備兵を徹底的に合理化し訓練したようです。
また、特定の場面でしか使われることのなかった大砲を有効に使い、歩兵・騎兵・砲兵の三兵を揃え有効に使ったことも特徴のようです。当時はパイク兵(大槍)の歩兵の方陣による白兵戦が主流だったようですが、それを三兵の有効性に変えたようです。
これもマウリッツの考えから端を成しているようですが、歩兵においては隊形とマスケット銃の軽量化を行い、砲兵においては攻城戦にしか用いなかった大砲を野戦に投入し、さらに騎兵においては小銃騎兵から抜刀突撃兵に改編し、機動性のある軍隊を作ったようです。
これによって、ヴァレンシュタイン率いる大軍に見事に勝利しました。
ただ、スウェーデン軍も、徴兵による常備兵のみだと人口の少ないスウェーデンにおいては働き手がいなくなり、深刻な打撃をこうむり、反乱が起こってしまい、この戦いのときには多くの外国の傭兵部隊を雇っていたようです。中核はあくまで訓練の行き届いた徴兵制常備軍でしたが。
※『傭兵の二千年史』菊池良生・講談社現代新書・2002とhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%84_(%E3%82%AA%E3%83%A9%E3%83%8B%E3%82%A8%E5%85%AC)参照
2章・フランスの三十年戦争の参入➀遠因

三十年戦争の第三ラウンドに活躍したグフタス・アドルフでしたが、その挙兵はフランスの作用があったのも一要因でした。
カトリックの国であったフランスがプロテスタント軍であるスウェーデン軍と関係を持ったのは、皇帝やスペインの王の血族である「ハプスブルク家」と対抗するという意図がありました。
ただ単に「反ハプスブルク家」というよりは、ルイ13世の宰相リシュリューによって進められたフランスという国自身を強くするという政策に基づいたものでした。
■①戦争を指揮する僧侶■
フランス国内におけるカトリックとプロテスタント勢力による激しい40年間の「ユグノー戦争」をプロテスタントも認めるという「ナント勅令」を出すことで鎮めたアンリ4世でしたが、1610年狂信的なカトリック教徒におって暗殺されてしまいました。
そこで、ルイ13世が王位を継ぐのですが幼かったため、アンリ4世の后でありルイ13世の母親であるマリー・ド・メディシス(サン・バルテルミの虐殺などで有名なカトリーヌ・ド・メディシスとは同族)が摂政となります。
そのもとで巧みわたり、1624年に国務会議の長として権力の最高地位になったリシュリューが現れます。
リシュリューは枢機卿でしたが、この時代は僧侶も軍の指揮をしても不思議がるものはあまりおらず、プロテスタントであるユグノーの鎮圧の戦争である1628年「ラ・ロシェル包囲戦」において指揮をとり見事にユグノーを平定しています(因みに「三銃士」はこの包囲戦のユグノー側にいた設定になってます)。
そして見事な活躍をしてついには1631年にマリー・ド・メディシスを追放し、ルイ13世のもとで権力を振うことになります。
リシュリューは、カトリックやプロテスタントのどちらかの徹底よりも、フランスという国、そして王権の強化を徹底し、特に諸外国に対してフランスの地位を上げることに尽力しました。
国内の治安においてはカトリックとユグノーのという構図だけでなく多くの武力を持った勢力に分かれていて、決闘が絶えず行われていたようです(この時代にフランスにいたデカルトも決闘を行っています。また「三銃士」もこの時代)。この決闘は戦争と内乱に劣らないくらい人口の減少に繋がっていてリシュリューは徹底的に決闘禁止令を処罰を厳重化し促します。また、国内の勢力の武力を削ぐ政策も行っていますが、国内の治安を良くするというよりは、王権の強化と諸外国への対抗への側面が強く、治安自体はまだ乱れていたようです。
■②北イタリアでの争い■
北イタリアは16世紀にスペインとフランスが領土争いをした土地でもあり、フランスとスペインの領土がありました。
スペインにとっては同じハプスブルク家であり皇帝がいるオーストリアとの連絡路として、北イタリアの制圧は重要でした(地中海を通して、北イタリアで上陸し陸路でオーストリアに向かう)。
一方、フランスにとってはもともとはイタリア・ルネサンスの高度な文化を取り入れることと、更にスペイン・オーストリアの「ハプスブルク家」の勢力を抑えるためにも重要な拠点でした(フランスの南東側と接しているため)。
そのため、1627年にはマントヴァ公ヴィオンツォ2世(1世はかつてのルーベンスの庇護者でもあった)が崩御してフランスとハプスブルクで継承争いが起きていました。
リシュリューもラ・ロシェル包囲戦で勝利した後その足で、ルイ13世とともにこの継承争いに参加し勝利しています(ただしこれによりスペインの北イタリアの総督は1625年にブレタ開城で活躍したスピノラという名将がつき、緊迫は続きますが)。
この戦いではフランスはプロテスタントを支援した側面もあり、スペインや皇帝だけでなくローマ教皇をも敵に回したようです。
このハプスブルク家との戦いがフランスの三十年戦争の参加の遠因になっていきます。
※『ルイ14世の世紀』ヴォルテール(訳)丸山熊雄・岩波書店・1958、やブログ「キリスト教で読む西洋史」、 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC を参照
3章・フランスの三十年戦争の参入②参入

ルイ13世が三十年戦争に参加したステップとしては、ルイ13世の絶対主義を宰相リシュリューが強化→ハプスブルク家が障害に→イギリスとの同盟模索→スウェーデンなどプロテスタントと同盟→そして遂に表舞台にという流れで登場します。
■①ルーベンスの活躍■
その後、リシュリューはさらなるフランスの国力の強化のためにイギリスとの同盟を考えました。
かつて1627~28年のリシュリューが指揮した「ラ・ロシェル包囲戦」においてはユグノー側をイギリスのチャールズ1世が支援していました。しかし、リシュリューがユグノーを平定したため、イギリスとの同盟を考えたのだと思います。
しかし、画家でありながら外交力にも長けていたルーベンスが1630年にあらゆる人脈を使い、イギリスとスペインの講和を制定してしまいます。
ルーベンスはフェリペ4世の庇護も受けていたためスペインの外交を手伝ったのですが、この講和の際にチャールズ一世から依頼された天井画「ジェームス一世の戴冠」などの作品も描き上げています。
これによってフランスのイギリスに対する目論見が失敗に終わり、フランスの宰相リシュリューはスウェーデンの同盟の模索と、スウェーデンを焚きつけて三十年戦争に参加せることを考えます。
■②スウェーデンの参入決断■
1631年、フランスは「ベールヴァルデ条約」を結びます。
条約内容は、カトリック皇帝軍の攻勢で苦境に陥った北ドイツ・プロテスタント諸侯を救うために、カトリック諸侯を救うために、カトリック・フランス王国の資金でスウェーデンがドイツに侵攻するというものでした。
もともとスウェーデンが三十年戦争に参入を考えたのは皇帝家ハプスブルク家が北ドイツに覇を唱え、バルト海制海権を狙って帝国バルト艦隊建造を宣言し、スウェーデンの国庫を支える大きな柱である重商主義的バルト海政策を侵す危惧があったためでした。
そして、同じ年にマリー・ド・メディシスを追放しカトリック一辺倒より王権の強化を優先し「反・ハプスブルク家」を掲げた大国であるフランスが資金を出すため、スウェーデンの決断したと考えられると思います。
但し、フランスはここでもローマ・カトリック教会から非難を受けています。
■③英雄死と泥沼化■
スウェーデンの参入もあり1631年のブライテンフェルトの戦い(ライプツィヒ近郊)においてプロテスタントが皇帝側に対して大勝利を収めます。
そのため皇帝軍はかつて大軍を揃えるシステムを運用し活躍しつつも権力を志向するようになったため罷免したヴァレンシュタインの復帰を検討し始めます。
そして1632年に皇帝のもとのヴァレンシュタイン軍とプロテスタントのもとのグフタス・アドルフのスウェーデン軍の「リュンツェン会戦」が行われ、スウェーデン軍が勝ちますがグフタス・アドルフが戦死したため、ヴァレンシュタインはプロテスタント諸侯と上手い関係を築く講和を模索し始め皇帝の敵となりかねなかったため、ヴァレンシュタインも1634年に暗殺されるという事態になります。
ただ、三十年戦争はグフタス・アドルフの英雄死によってプロテスタントも戦いを辞めることを選択する事はなく、またスペインと皇帝のオーストリアは互いに新しい王が即位し新鋭となり戦争に積極的になり、兵士も戦争遂行能力を支える肥沃な大地(オーストリアあたりの戦場周辺)が不毛な地へと荒れ果ててしまったため食うために生きるために傭兵となるしかなく、戦争は泥沼に続いていきます。
■④フランスの参入■
1634年ネルトリンゲン会戦において、皇帝嫡男フェルディナンドとフェリペ三世の三男フェルディナンドの両ハプスブルク家の新鋭がタッグを組んで巻き返しを図り、スウェーデンとドイツ新教軍に大勝利を収めてしまいます。
そして1635年に「プラハ条約」において、新教を認める代わりに皇帝権が承認され、ハプスブルク家の力が強くなってしまう危惧から、ついにフランスが表舞台に出ることを決断し、三十年戦争に参入していきます。
※『ルイ14世の世紀』ヴォルテール(訳)丸山熊雄・岩波書店・1958、『傭兵の二千年史』菊池良生・講談社現代新書・2002やブログ「キリスト教からみる西洋史」、 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC を参照